婦人科での麻酔まとめ【前編】
子宮がん検査、ミレーナなど、痛みを和らげる方法と種類を徹底解説
婦人科で受ける処置や検査に、痛みや不安を感じたことはありませんか?
「ミレーナに興味があるけど、挿入が痛いって聞くから怖い」「子宮がん検査のとき、麻酔はしてもらえる?」──そうした疑問や不安から、受診をためらってしまう方も少なくありません。
実際、婦人科では検査や処置の内容によって、痛みの感じ方もさまざまです。そして、必要に応じて使える麻酔の種類もいくつかあり、自費か保険適用かで費用も異なります。
本記事では、婦人科で行われる痛みを伴う主な処置の内容と、それぞれに使われる麻酔の種類や特徴について、できるだけわかりやすく解説していきます。
なお、今回の解説は、「婦人科外来」で行われる検査やミレーナ挿入、初期中絶などを対象としています。無痛分娩や中期中絶など、お産の痛みに関しては、別記事で詳しく解説しますのでお楽しみに。
婦人科で行われる痛みを伴う処置とは?
婦人科で行われる処置のなかには、身体的な痛みや精神的な緊張を伴うものもあります。ここでは、よく行われる検査や治療の中で、SNSなどでもたびたび話題になる、痛みを感じやすいとされる代表的な処置についてご紹介します。それぞれの処置にどのような痛みがあるのかも含めて解説していきます。
クスコ診の痛み
検査や子宮内部の観察が必要なとき、まずクスコ(腟鏡)という器具を挿入します。これは、おりものの状態や出血の様子、子宮内部にポリープなど異常がないかを医師がチェックしたり、検査のために細胞をとるためのブラシの通路を確保するためにするものです。
器具そのものは細いので、性交渉の経験がある方であれば、さほど痛みは感じませんが、この器具の挿入時に痛みを感じる人はいらっしゃいます。

子宮頸がん検査や子宮体がん検査での痛み
子宮がん検査には、大きく分けて3つの種類があります。子宮頸がん検査(細胞診)、コルポスコピー検査、子宮体がん検査(細胞診、組織診)です。
子宮頸がん細胞診は、子宮の入り口を柔らかいブラシでこすり、細胞をとる検査のことです。これはハケのような形をしたシリコンのブラシで表面をこすって数秒で終了するため、あっても違和感程度で、痛みを伴わないことがほとんどです。(このとき、クスコを挿入するため、その痛みはある場合もあります)
子宮頸がん検査のうち、細胞診で引っかかった方が精密検査で行う「コルポスコピー+組織診」は、子宮の入り口から小さな組織を器具でパチンと採取するため、瞬間的な鋭い痛みが走ることがあります。
また、子宮体がんの検査で子宮内膜を採取する場合は、子宮の奥、つまり赤ちゃんの通り道である子宮頸管を通って子宮の内部に器具を挿入するため、生理痛のような痛みや違和感を感じることが少なくありません。特に、お産の経験がない方や、子宮口が硬い方は痛みが強く出やすかったりします。
ミレーナの挿入・抜去時の違和感や痛み
ミレーナ(黄体ホルモンを子宮内に放出する器具)の挿入・抜去は、通常数分で終わる処置ではあるものの、子宮頸管を通って子宮の内部にミレーナを挿入するので、子宮口の通過に際してズーンと重く引かれるような、生理痛のような痛みを感じる方が多くいます。特に未経産の方や子宮の傾きが強い方は痛みが強く出やすく、「ミレーナは痛い」という言説はここからきています。
ただし、痛みには個人差がかなり大きく、「えっ、入ったんですか?!」というくらい何も感じない方もいれば、挿入後に生理痛のような重い痛みが強く、しばらく院内でお休みになられてから帰路につく方まで、色々な方がいます。やはりお産の経験のある方が一度お産で子宮頸管が広がっているため痛みが軽い傾向にありますが、未経産の方でもケロッとしている人は一定数いらっしゃいますので、一概にはいえません。
なお、抜去は挿入と比べると比較的軽い痛みか、ほとんど感じない程度ですが、それはスムーズに抜けたときの話で、紐が行方不明になってしまっているなど処置が難航した場合には、痛みを伴う場合もあります。
初期流産の子宮内容除去術(吸引法、掻爬法など)
妊娠初期に流産と診断された場合、自然排出を待つ方法もありますが、子宮内に遺残がある場合は「子宮内容除去術」という処置を行うことがあります。この手術は、子宮の内容物を除去するため、痛みを伴う処置であり、静脈麻酔を用いて全身を軽く眠らせるか、局所麻酔やブロック麻酔を併用します。流産や中絶は心身の負担が大きい状況であるため、十分な麻酔管理が必要になります。
経腟超音波や内診
通常、経腟超音波や内診は大きな痛みを伴いませんが、過去のトラウマや子宮や腟の解剖学的な特徴(腟の狭さや子宮の位置など)、子宮内膜症で癒着があるといった場合には強い痛みを感じる方もいます。
人工妊娠中絶に用いられる麻酔と注意点
妊娠12週未満の人工妊娠中絶では、流産の処置と同じように、日帰りでの子宮内容除去術を行うのが一般的です。点滴で鎮静薬を投与し、意識を落とした状態で処置を行うもので、患者さんは処置中の記憶がほとんど残りません。痛みへの配慮だけでなく、精神的ストレスの軽減も目的とされています。中絶については、こちらの記事でも詳しく紹介していますので参考にしてください。
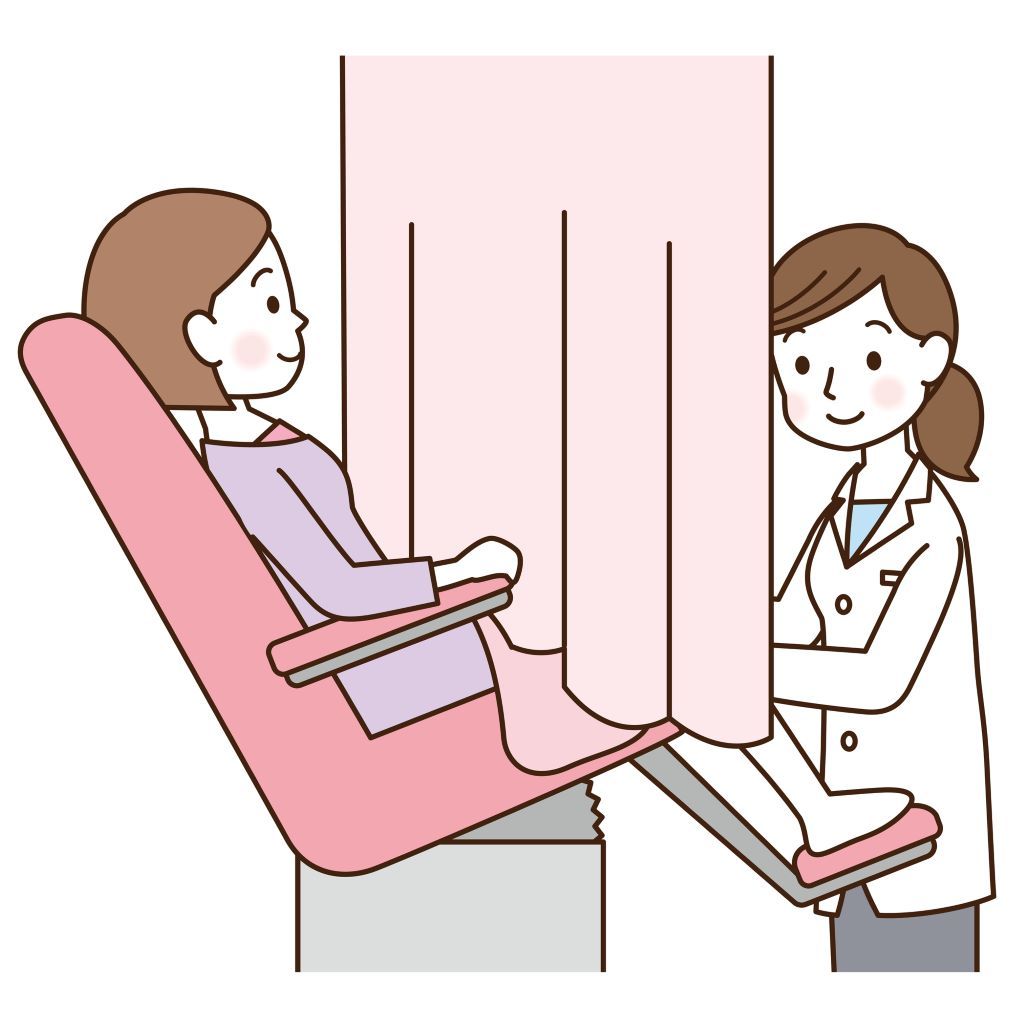
麻酔にはどんな種類がある?
医療機関で痛みをやわらげるために使われる麻酔には、実はいくつか種類があり、目的や体の状態に応じて使い分けられています。婦人科の外来でよく使われる麻酔について、そのしくみや特徴、どのような場面で用いられるかを整理してみます。
浸潤麻酔(麻酔ゼリー)
浸潤麻酔は、腟の入口の表面に麻酔のゼリーを塗布する方法です。痺れた感じになり、痛みの軽減効果は高い一方で、あくまで表面のみの麻酔なので、腟の奥や子宮口付近の痛みまでは取れません。
ブロック麻酔(傍頸管ブロック、頸管内ブロック)
ブロック麻酔とは、特定の神経に作用させる麻酔で、婦人科では「頸管ブロック」と呼ばれる子宮頸部への注射が主に用いられます。麻酔自体にも注射の痛みはありますが、子宮の入り口である頸部を麻痺させることで、器具で子宮の入り口を掴んで支えたり、子宮頸管を広げる痛みの軽減が期待できます。
笑気麻酔(吸入式のリラックス麻酔)
笑気麻酔とは、酸素と亜酸化窒素(N₂O)を混ぜた気体を吸入することで、鎮静・鎮痛作用が得られる麻酔方法です。眠ってしまうわけではなく、意識があるまま、酔っ払った感じのイメージで、緊張や不安がやわらぐのが特徴の麻酔です。婦人科では、ミレーナの挿入時や検査の際の痛みが心配な方に使用されることがあります。作用は短時間(20〜30分くらい)で消失し、安全性も高いため、麻酔への不安が強い方にも適しています。ただし、痛みが取れる訳ではないので、浸潤麻酔やブロック麻酔と併用します。

静脈麻酔(点滴で眠らせる麻酔)
静脈麻酔は、腕の静脈から鎮静薬を点滴で投与し、意識レベルを下げる方法です。点滴が必要なので針の刺入・留置に伴う痛みや血管痛が起こります。意識消失に伴い痛みは感じなくなりますが、呼吸や循環の管理が必要になるため、専門家の管理下でのモニタリングや回復室での観察が求められます。
当然、大掛かりな設備や医療スタッフの確保、麻酔が覚めるまで患者さんを寝かせて管理しておくためのスペースも必要です。また、呼吸が止まるなどといった、重篤な副作用も起こりえるほか、目が醒めるまでに時間がかかります。このため、基本的に静脈麻酔ができるのは大きな病院に限られ、一般外来診療には不向きなのです。
なぜ婦人科の検査や処置には麻酔を使えないの?
婦人科の処置に「麻酔なし」で行われるものが多いことは、たびたびSNSでも話題になっています。「なぜ痛みがあるのに麻酔してくれないの?」と感じるのはもっともなのですが、ただ、そこには医療者側が配慮していないとか、怠慢といった話ではなく、医学的・技術的な事情がきちんとあります。
子宮の痛みは、歯の治療のように簡単には取れない
歯科治療では局所麻酔をすれば「ほとんど無痛」と感じられることが多いですが、婦人科の場合はそう簡単ではありません。子宮は骨盤内の深部臓器にあり、そこに直接麻酔を効かせることは技術的に難しく、たとえ注射しても一部しか麻痺しないことが多いのです。表面に塗って感覚を麻痺させたり、注射をしても、体の奥にある子宮の痛みを「完全に取る」には限界があります。麻酔が使われていないからといって、必ずしも痛みを軽視しているわけではない、という点をご理解いただければと思います。
麻酔自体にも痛みや命に関わるリスクがある
ぜひ知って頂きたいのは、全ての麻酔にはアナフィラキシーなどの薬剤による副作用のリスクが伴うということです。「痛みを取るための麻酔注射」ですが、その注射そのものが痛みを伴うこともあります。子宮頸部へのブロック麻酔は、注射針を粘膜に刺すため、「かえって痛い」と感じる方もいます。処置自体がごく短時間で終わる場合などには、あえて麻酔を使わずに処置を行う判断がされることもあります。
「採血や注射には麻酔はしないのが一般的」必要性とバランスの問題
医療現場では、処置や医療行為におけるリスクとベネフィットをきちんと考えないといけません。たとえば、採血やワクチンを打つときには痛みがありますが、事前に麻酔をすることはまずありませんし、みなさんも経験がないと思います。婦人科の処置においても、痛みの程度・処置の時間・患者さんの体質などを踏まえて、「麻酔を使うことでかえって負担が増えるかもしれない」と判断されるケースがあるのです。痛みをとる麻酔に使われるキシロカインにはアレルギーもあるため、あえて採用していない医療機関もあります。
多くの医療機関で検査に麻酔をしない背景には、こうした現実的なバランスもあることをご理解いただければ幸いです。
保険適用の処置でも、麻酔の併用で自費負担に
婦人科の処置には、本来は保険適用となるものが多くあります。たとえば、月経困難症の治療目的でミレーナ(子宮内黄体ホルモン放出システム)を使用する場合、原則として保険診療の対象です。しかし、ここに笑気麻酔など「自費の麻酔オプション」を組み合わせると、処置全体が「自由診療扱い」となり、ミレーナ本体の代金も含めて全額自費になってしまいます。
これは、日本の医療制度において「混合診療(保険と自費を同時に行うこと)」が原則として禁止されているためです。保険診療内で認められていない麻酔を加えると、保険でカバーされるはずの診療行為も自費と見なされ、結果的に患者さんの自己負担が増えるという、ルール上の事情もあるのです。
海外でも、ミレーナ挿入時の麻酔はそんなに一般的ではない
実際のところ、ミレーナ挿入時の局所麻酔使用は、痛みを軽減するというエビデンスが十分になく、海外での使用率もそこまで高い訳ではありません。「海外では当たり前」などといった情報を流している人がいますが、実際はそうではないようです。
IUS、IUD挿入時の局所麻酔の使用はイギリス43%、オーストリア31%、チェコ1%、スペイン2%、フィンランド3%、イタリア3%、フランス6%、ポーランド7%、ドイツ10%、スウェーデン11%、とのこと。オーストラリアでは64.2%に局所麻酔が使用されていたという文献もありました。アメリカでは、鎮痛薬は使われるものの、局所麻酔はまれとのことです。

まとめ|「麻酔がないのはおかしい」と感じているあなたへ
婦人科の処置における痛みと麻酔の問題は、メディアではほとんど語られてこなかったと思います。「なぜこんなに痛いのに麻酔をしてもらえないの?」「もっと配慮があってもいいじゃん!」そう感じるのは、決して特別なことではありません。
ここまでは、婦人科で行われる処置ごとの痛みの程度や麻酔の種類、そして麻酔が使われにくい背景にある医学的・制度的な事情について解説してきました。
子宮という臓器の構造的な特性や、麻酔のリスク、そして医療制度上の制約など、納得できる理由もあったのではないでしょうか。
生理や出産など、女性の痛みは確かに軽視されてきたように思います。しかし、SRHRの視点からも「痛みは我慢すべき」という考えは時代遅れですし、断言しますが、「痛みに意味はありません」。痛みに弱いので多少のお金は払うから麻酔をしてほしい、という方は少なからずいらっしゃいます。今は配慮のある医療機関もたくさんあるので、ぜひ問い合わせてみてください。
次回の後編では、実際に麻酔を希望するときにどんな準備や注意点があるのか?受診の際に、痛みを感じないために自分でできることは?といった受診前に知っておきたいポイントを解説していきます。どうぞお楽しみに。
【参考文献】
産婦人科外来診療・小手術の局所浸潤麻酔・伝達麻酔 竹田省 メジカルビュー社,2022
オーストラリアでは64.2%に局所麻酔が使用されていたとの文献。
Blaire D et al., ACOG 2018(2), 236.e1-e9, 2018
















