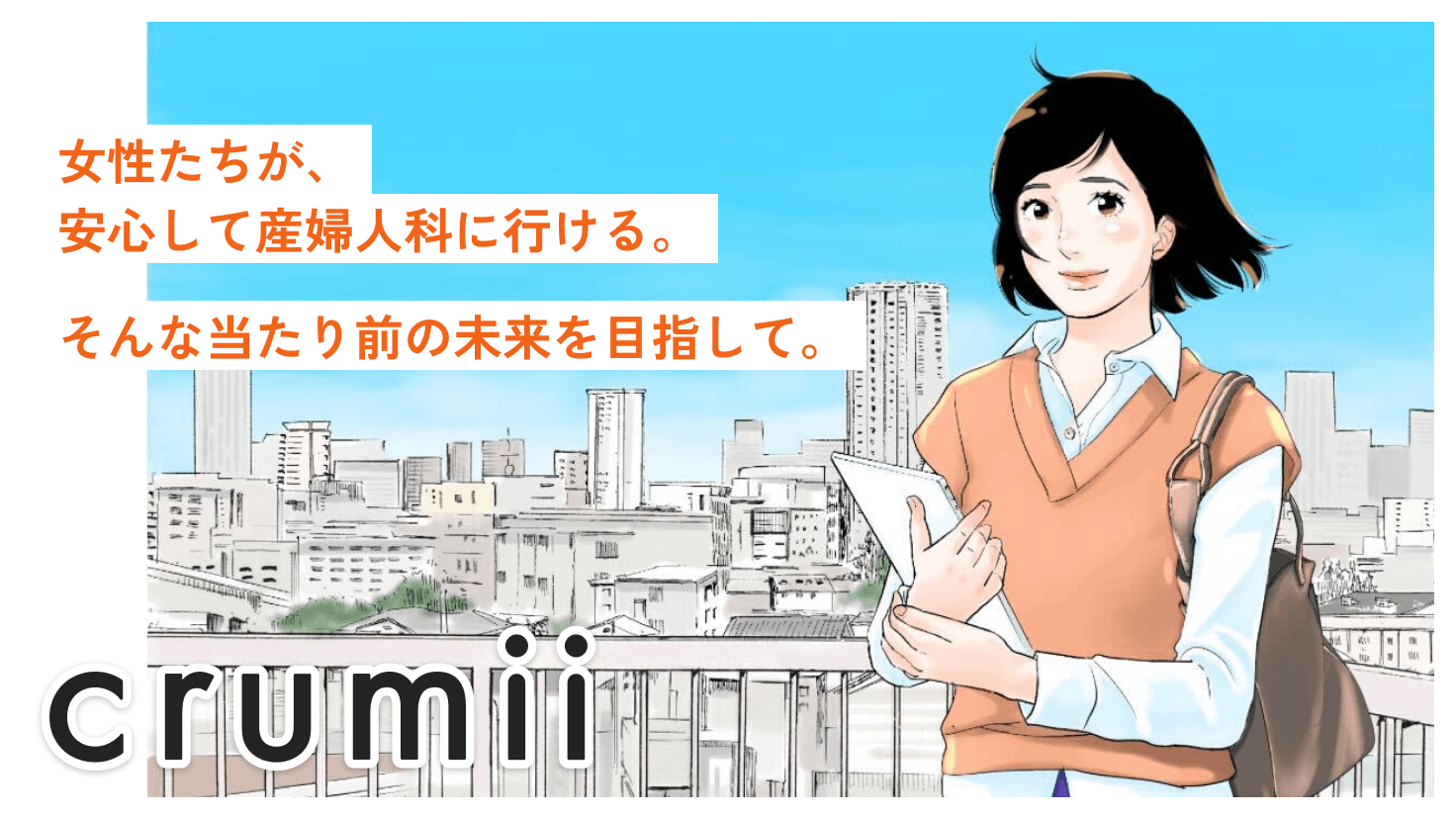産婦人科医療とAIの最前線:日常診療への応用と未来展望
人工知能(AI)は医療の様々な分野で急速に発展しており、産婦人科領域でも日常診療への実装が始まっています。妊娠中のリスク予測や分娩監視、不妊治療の効率化から婦人科疾患の診断支援まで、最新のAI技術が臨床に活かされつつあります。本記事では、産婦人科の日常診療におけるAI活用の具体例と現状、そして課題や将来展望について、わかりやすく解説します。
妊娠管理へのAI活用 – リスク予測と早期対策
妊娠中の合併症リスクを早期に察知し、母子の安全を守るためにAIの活用が期待されています。例えば、妊娠高血圧症候群(子癇前症など)の発症リスク予測では、機械学習モデルが有望です。2025年に発表された研究では、網膜画像と母体の血圧などから子癇前症を非侵襲的に予測するAIモデル「PROMPT」が開発されました。妊娠14週以前の妊婦1,812人分のデータで検証した結果、PROMPTは重症の妊娠高血圧症候群を高い精度(AUC 0.87)で予測し、従来法と比べて重篤な妊娠転帰を検出する感度を35%から41%に向上させたと報告されています。このようなAIによる早期リスク評価によって、ハイリスク妊婦を見逃さずに適切な管理や早期介入につなげることが可能になります。
出産の安全を支えるAI – 分娩予測と帝王切開の判断支援
お産の現場でもAIが力を発揮し始めています。分娩中に用いる胎児心拍モニタ(CTG)の波形をAIで解析し、胎児が危険な状態に陥る前に異常を検知しようという試みが進んでいます。近年の研究では、約27,000例以上の分娩データを用いて深層学習モデルを開発し、分娩中に出生児が低酸素血症(酸欠)になるリスクを高精度に予測することに成功しました。このモデルは、多施設データを用いた検証で重度の胎児低酸素血症を検出するAUC 0.74〜0.83という成績を示し、従来人間の目視に頼っていた胎児モニタ監視をAIで客観化できる可能性を示しています。異常の兆候を早く正確に察知できれば、緊急帝王切開の判断までの時間的余裕が生まれ、母子の安全性が高まるでしょう。実際、通常は胎児機能不全と判断されてから、可能であれば30分以内に帝王切開開始が求められますが、AIが異常検知を10分以上早めることができれば、その余裕は母体・胎児双方の命を救う上で極めて大きな意味を持ちます。さらに、AIは帝王切開の意思決定支援にも応用され始めています。現在、医学的指標に基づき「帝王切開に踏み切るべきタイミング」をAIが提案できないかという研究も進められており、経験や勘に頼りがちな判断をデータで後押しする試みとして注目されています。また、産婦人科医不足を補うため、遠隔地の妊婦を対象にAIによる胎児モニタリングの実証も行われています。離島や自宅にいる妊婦の心拍データをAIが常時解析し、異常時には専門医が遠隔で対応するといった仕組みも試験導入が始まっています。

婦人科診断とAI – 画像解析で早期発見を支援
婦人科疾患の領域でも、AIは医師の診断をサポートしています。特に画像診断との親和性が高く、子宮頸がんや子宮内膜症、子宮腫瘍の診断で有望な成果が報告されています。
子宮頸がん検診では、AIによる画像解析が精度向上に寄与する可能性があります。米国NIHの研究チームは子宮頸部の写真画像から前がん病変を発見するディープラーニングアルゴリズムを開発し、その有用性を検証しました。コスタリカで収集された6万枚以上の子宮頸部画像データ(約9,400人分の長期追跡情報付き)で訓練したこのAIは、前がん病変の検出精度(AUC)0.91を達成し、これは熟練細胞診専門医による顕微鏡検査(AUC 0.69)や従来の細胞診法(0.71)を上回る成績でした。スマートフォンなどで子宮頸部の画像を撮影するだけで安価にスクリーニングが可能となるため、医療資源の限られた地域でも高精度な検診が期待されています。
子宮内膜症の診断にもAIが役立ちます。内膜症は画像診断が難しく見逃されやすい病気ですが、近年のレビューによるとMRIや超音波画像とAIを組み合わせることで診断精度を大きく向上できる可能性があります。2022年の報告では、内膜症にAIを適用した複数の研究を分析し、病変の検出感度が平均81.7%から最大96.7%、特異度も70.7%〜91.6%に達したとまとめられました。これは熟練医による読影を上回るケースもあり、AIが内膜症の見逃しを減らし早期発見に貢献できることを示唆しています。
日本発の研究例としては、子宮肉腫(まれだが予後不良な子宮体がんの一種)の術前診断AIが注目されます。東京大学の研究グループは、MRI画像から良性の子宮筋腫と悪性の子宮肉腫を識別するAIシステムを開発しました。その成果によれば、開発したモデル(AutoDiag-AI)は交差検証で正診率89.3%(感度90.5%、特異度88.9%)を達成し、新たな検証用データセットでも正診率92.4%(感度92.3%、特異度92.5%)と高精度を示しました。従来は専門医でも鑑別が難しかった症例に対し、AIが術前に悪性の可能性を示唆できれば、不要な手術を避けたり早期の根治手術につなげたりできる可能性があります。現在、このAIの臨床応用に向けた更なる検証が進められています。

生殖医療とAI – 胚選別から不妊治療支援まで
体外受精(IVF)など生殖医療の分野でもAIの導入が進んでいます。培養した受精卵(胚)の中から着床しやすい良好胚を選別する工程にAIを活用する技術が登場しました。米国のコーネル大学の研究チームは、BELAと名付けられたAIシステムを2024年に発表し、Nature誌の姉妹紙で詳細を報告しています。このシステムは培養胚のタイムラプス動画から胚の形態スコアを自動算出し、母体年齢と合わせて胚の染色体異常(異数性)の有無を予測します。特徴的なのは、従来必要だった熟練胚培養士による主観的評価を介さず、完全自動化された客観的な指標で胚の状態を判定できる点です。開発チームによれば、BELAは従来モデルよりも高い精度で胚の正常・異常を分類でき、独自データセットで胚の染色体正常/異常を識別するAUC 0.76を達成しました。これは胚培養士の評価を用いる従来AIモデルと同等の精度であり、外部の別施設データでも良好に機能したとされています。BELAのような技術が臨床試験で有用性を示せば、着床前診断(PGT-A)のような侵襲的かつ高コストな遺伝子検査に頼らずとも、移植すべき胚を高精度に選別できる可能性があります。世界中どのクリニックでも導入しやすいソフトウェアとして提供されれば、不妊治療の成功率向上や地域格差の是正にもつながるでしょう。
医療現場の効率化 – AIが支える新しい働き方
産婦人科の診療現場では、患者対応や記録業務の負担軽減にもAIが役立ち始めています。電子カルテ入力補助として、医師と患者の会話をそのままAIが文字起こしし、カルテの下書きを自動生成する音声入力システムが登場しました。診察中に会話を録音すると、AIがその内容を要約してSOAP形式の記録案を作成する仕組みです。医師は後でそれを確認・修正するだけでよく、キーボード入力の手間を大幅に減らせます。こうしたAI音声起こしツールは米国を中心に「アンビエント(環境型)AI」として発展しており、初期報告では診療後の記録業務時間の短縮や医師の燃え尽き症候群(バーンアウト)軽減につながったとの指摘があります。実際、診療中に画面入力する必要が減ることで医師が患者と向き合う時間が増え、患者満足度も向上したとの報告がなされています。一方で、AIによる記録には誤りや不正確な要約が入り得ること、データのプライバシーやAIへの過度な依存による「認知的負債」の問題など課題も指摘されています。そのため、こうしたAIクラーク(電子カルテ代行)は医師の最終チェックを経て活用することが重要です。
また、AIチャットボットも産婦人科領域で活用されています。患者からの問い合わせ対応や健診結果の説明など、比較的定型的なやり取りを自動化する試みです。自治体では妊娠・出産・子育てに関する24時間対応の相談チャットボットが導入され、時間や場所を問わず不安や疑問を解消できる窓口として注目されています。例えば自治体の公式サイト上で妊娠週数や症状を入力すると、AIが蓄積された知識にもとづきパーソナライズされた回答を返してくれる仕組みです。海外でも同様の取り組みが進んでおり、AIアシスタントによる妊産婦支援の有効性を検証する研究も出てきています。2025年の報告では、産後の母親を対象としたAIチャットボットによる育児支援アプリの利用で、従来の冊子配布に比べて母親の育児自己効力感(自信)と母乳育児の成功率が有意に向上したとの結果が示されました。このようにAIチャットボットは、妊産婦が抱える悩みに対して個別に寄り添うツールとして期待されています。ただしチャットボット単独で完結するのではなく、必要に応じて人間の専門家(医師や助産師)につなぐ仕組みを組み合わせることで、安心して利用できるサービスとなるでしょう。

現状の課題と将来展望
産婦人科領域におけるAI活用は大きな可能性を秘めていますが、実用化に向けて乗り越えるべき課題もいくつかあります。まず、データの質と量の問題です。AIの性能を上げるには大量の高品質データが必要ですが、特に合併症や希少疾患の症例データは限られています。日本では電子カルテや健診情報の標準化・データ共有が十分でなく、AIモデルの汎用性を高めるには今後の環境整備が不可欠でしょう。また、AIの判断根拠が不明瞭になりがちな「ブラックボックス問題」も臨床応用上の懸念です。命に関わる医療判断をAIに委ねるには、結果の説明可能性(なぜその結論に至ったか)を確保し、医師が最終確認する仕組みが欠かせません。さらに、倫理面・プライバシー面への配慮も重要です。妊娠・出産や生殖医療はデリケートな情報を扱うため、個人情報の保護やAIのバイアス(偏り)除去にも十分な注意が必要です。AIモデルは学習データの偏りをそのまま反映してしまう恐れがあり、公平性を担保する取り組みや法規制も求められます。
こうした課題を一つひとつ乗り越えながら、産婦人科におけるAIは今後ますます発展していくでしょう。将来的には、超音波検査中にAIが異常所見をリアルタイムで指摘したり、分娩の進行をリアルタイム分析して最適な介入タイミングを提案したりすることも考えられます。また、対話型AI(生成AI)の進化により、自然な会話で妊婦の悩みに寄り添うバーチャル助産師の登場も期待されます。例えば音声アシスタントに妊婦が相談すると、AIが即座に適切なアドバイスや受診判断を提供し、必要に応じて人間の専門家につなぐといった未来像です。ただし、AIはあくまで道具であり、最終的な判断や患者への共感・ケアは人間にしかできません。AIが煩雑な作業や情報分析を担い、人間の医療者がより高度な判断と患者に寄り添った丁寧なケアに専念できるようにすることが、未来の理想的な医療体制でしょう。現状、AI導入は始まったばかりですが、慎重に活用を進めていけば、医療者と妊産婦双方に安心で利益の大きい産婦人科医療の未来が拓けるはずです。
【参考文献(References)】
[1] Wu, Y. et al. “Noninvasive early prediction of preeclampsia in pregnancy using retinal vascular features.” npj Digital Medicine, vol. 8, 188, 2025 nature.com.
[2] Ben M’Barek, I. et al. “DeepCTG 2.0: Development and validation of a deep learning model to detect neonatal acidemia from cardiotocography during labor.” Computers in Biology and Medicine, vol. 184, 109448, 2025 pubmed.ncbi.nlm.nih.govpubmed.ncbi.nlm.nih.gov.
[3] Hu, L. et al. “An observational study of deep learning and automated evaluation of cervical images for cancer screening.” J. Natl. Cancer Inst., vol. 111(9), pp. 923–930, 2019 cancer.gov.
[4] Sivajohan, B. et al. “Clinical use of artificial intelligence in endometriosis: a scoping review.” npj Digital Medicine, vol. 5, 109, 2022 nature.com.
[5] Taguchi, A. et al. “Automatic diagnosis AI system for preoperative MRI of uterine sarcoma (AutoDiag-AI).” J. Gynecol. Oncol. (JGO), vol. 35, e24, 2024 ejgo.org.
[6] Rajendran, S. et al. “Automatic ploidy prediction and quality assessment of human blastocysts using time-lapse imaging.” Nature Communications, vol. 15, 7756, 2024 nature.com.
[7] Leung, T. I. et al. “AI Scribes in Health Care: Balancing Transformative Potential With Responsible Integration.” JMIR Medical Informatics, vol. 13(1), e80898, 2025 medicalxpress.com.
[8] Yildiz, G. K. et al. “Artificial intelligence-assisted chatbot: impact on breastfeeding outcomes and maternal anxiety.” BMC Pregnancy and Childbirth, vol. 25, 631, 2025 bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com