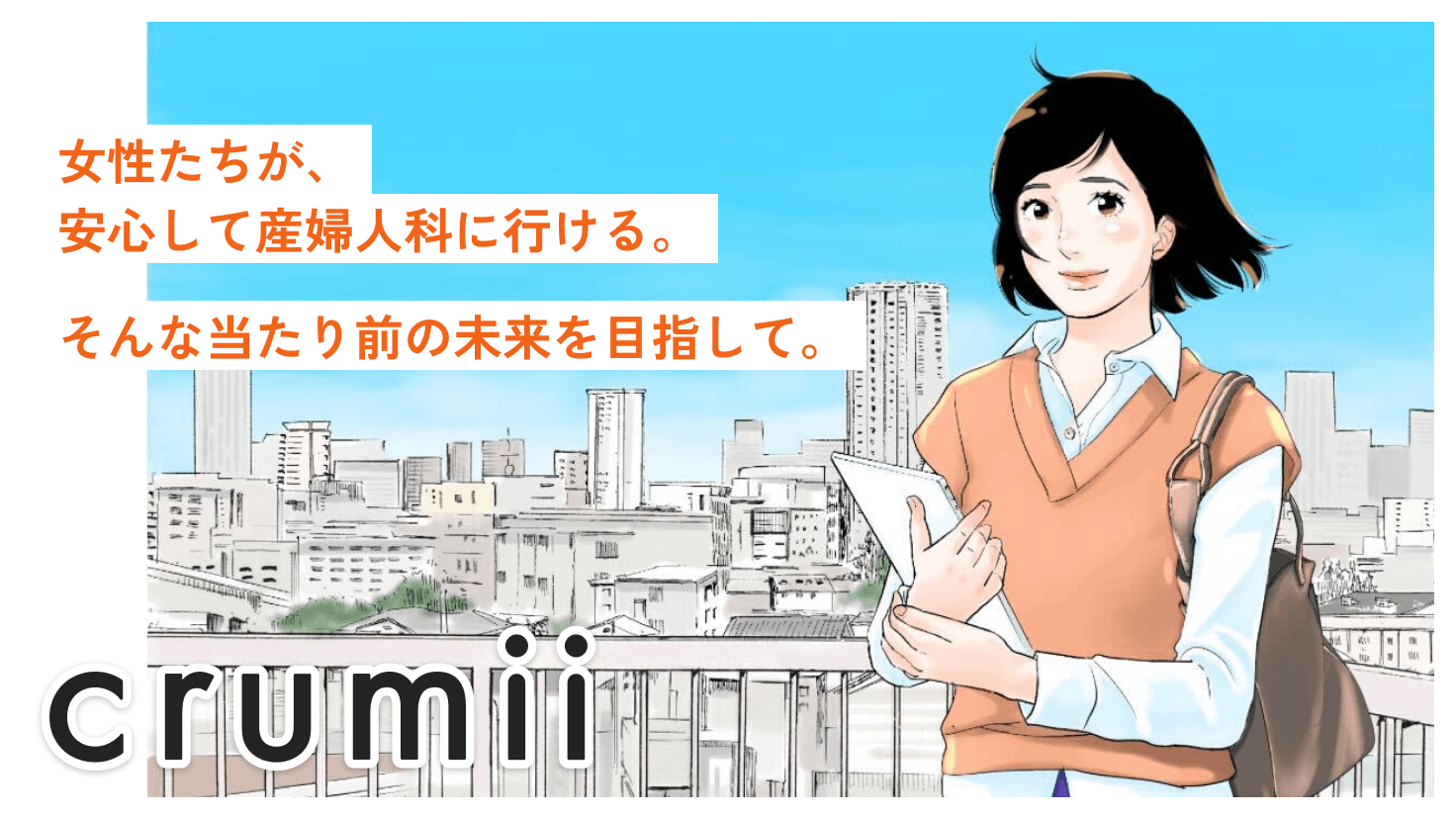#5 認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ所属・柳沢正和様リクエスト
人口のわずか1%しかいないトランスジェンダーが、なぜ取り沙汰されるのか。【クラウドファンディング・リクエスト記事】
2025年3月10日、クラウドファンディングが無事終了いたしました。おかげさまで、667名の方々から12,384,000円のご支援をいただき、「目標達成」という形で終了することができました。
こちらのコラムは、記事掲載リクエスト・コースでいただいたご希望に基づき、執筆されたものです。
支援者の皆様からは、医療にかかわる話題だけでなく、幅広く女性の健康とSRHR(すべての人が性と生殖に関する健康を享受し、からだの自己決定権を持ち、自分自身の意思で選択できる権利)にかかわるテーマをリクエストいただきました。
今回のテーマは認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ所属・柳沢正和様からリクエストいただきました「トランスジェンダー」です。
トランスジェンダーという語を見聞きする機会が増えました。性別違和のある人、または性別移行した人が登場するドラマや映画、漫画は、いまやめずらしくありません。特に欧米を中心に、センセーショナルに描くのではなく、ごく普通に社会生活を送る人としてトランスジェンダーが登場する作品も多く生み出されるようになりました。
その一方で、SNSではトランスジェンダーに関する”炎上”がたびたび起きています。苛烈な言葉が飛び交い、それがさらなる偏見や差別につながることもあるようです。
炎上の原因はほとんどの場合、誤解や思い込みからはじまっています。払拭するには、正しい知識が必要です。
ここからは、社会で生きる「ごく普通の人々」であるトランスジェンダーについての基礎的な知識と、取り巻く現状について解説します。
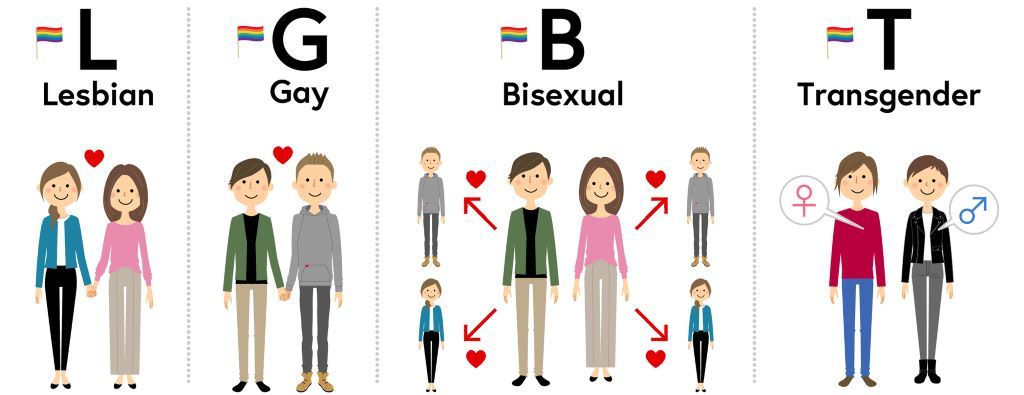
●トランスジェンダーとは、その性で生きたい人たち
出生時に割り当てられた性別とは異なる性自認(Gender Identity)を持つ人のことをいいます。
生まれたとき、ほとんどの人は医療従事者によって性別を告げられます。それは外性器を見て判断されたもので、さまざまなものに「女」または「男」と記録され、その後は多くの保護者や教育機関がその性別“らしく”育てようとします。
性自認とは、「自分をどんな性別(男性・女性・両方・いずれでもないなど)だと感じているか」という、自身の感覚のことです。
生まれたときに「女の子ですよ」と割り当てられ、そのように育てられたけれど、自分自身を「男の子である」と認識している人はトランス男性であり、その逆であれば「トランス女性」です。
男か女かだけでなく、性のあり方は多様です。
・ノンバイナリー:自分の性を「男でも女でもない」と感じる人。性別をふたつに分ける考え方に当てはまらない
・Xジェンダー:日本で生まれた言葉で、男性・女性のどちらとも違う、または両方にあてはまるなど、男女というふたつの区分では表せない性自認をもつ
などなど、誰にでも、その人なりの性自認があります。
対して、出生時に割り当てられた性別と性自認が一致している人は、シスジェンダーといわれます。いうまでもなく、マジョリティです。
国内の調査では、トランスジェンダーは人口の1.15%を占めると報告されています*。諸外国の調査でも1%前後となるようで、「100人に1人の割合」といっていいでしょう。
*電通「LGBTQ+調査2023」
●性別移行、何をどこまでするかは本人の自由
性別移行(トランジション)とは、自認する性に沿うように、見た目やふるまい、社会的な役割、そして場合によっては戸籍上の性別などを変えていく過程のことです。
ホルモン治療や生殖腺の切除、または乳房や性器など外見の特徴を変える外科手術などをするか、しないか、どの程度するかは人それぞれです。戸籍を変えるかどうかも、その人が決めることです。
トランスジェンダーかどうかは、身体の特徴や戸籍で決まるのではなく、本人がどのように自分の性を認識しているか、つまり性自認によって決まります。
トランスジェンダーとは、自認する性で社会を生き、生活をしたい人です。行きたいところに行き、食べたいものを食べ、親しい人と過ごしたい、希望する職に就きたい、好きな服を着たい、誰かと出会っていつかは結婚したい、あるいは、ひとり生きていきたい……。
しかし現状では、トランスジェンダーが自分らしく生きるのを妨げるものがたくさんあります。それらは大きく2種類に分けられます。
ひとつは、制度です。たとえば戸籍の性別を変えたいとき、いくつかの「条件」をクリアする必要があり、日本ではそれがとても厳しいものになっています。自認する性で生きるのと引き換えに人権を差し出さなければいけないようなものもあり、その歪(いびつ)な条件は国際的に強い批判が寄せられています。
ふたつめは、偏見や差別です。性のあり方の問題にかぎらず、偏見や差別の多くは誤解や思い込みに基づいたものです。ヘイト発言をするのは“悪い人”とはかぎりません。ただ知らないがゆえの誤解、よかれと思っての思い込みがヘイトにつながることはよくあります。

●偏見や思い込みに惑わされないために
以下、トランスジェンダーについてよくある誤解の一部をあげて、解説しましょう。
トランスジェンダーは病気でしょ。
かつては『性同一性障害(Gender Identity Disorder)』と呼ばれ、精神疾患とされていましたが、現在は疾患や障害ではなく、性自認にかかわる多様性のひとつとして理解され、「性別不合(Gender Incongruence)」という名称が使われています**。
**世界保健機関(WHO)は、国際疾病分類 ICD-11(2019年公表、2022年適用)において「性同一性障害」を精神疾患の分類から外し、「性的健康に関する章」に移行しました。
トランス女性=男性が女装しているだけだよね。
「性自認が女性である」と「服装の表現が女性である」は、まったく別の現象です。トランス女性は「女性として」社会生活を営みたい人、および営んでいる人を指します。職場や学校に女性として所属したい、周囲から女性として接してもらいたい。服装が女性らしいかどうかは関係なく、中性的であろうがボーイッシュであろうが、それはその人の自由です。
“本物”のトランスなら、戸籍を変えているよね。
先ほど少し触れたように、 戸籍変更には厳しい条件があり、ハードルが非常に高いです。一部を紹介すると、いわゆる「手術要件」というものがあり、生殖腺(卵巣・精巣)の除去については2023年に外されたものの、性器の外見についてはいまなお、「性器の外見を、移行したい性別にあわせて整える手術」を済ませていなければならないと法律で定められています。この手術要件は諸外国にもありますが、2020年代に入って先進国の多くが撤廃しています。
それ以前に、人の性自認を他者が「本物? 偽物?」とジャッジすること自体がおかしいです。
気分で性別を変えると社会が混乱するよ。
性自認は一度決めたら永続的にそうでなければならないものではなく、生涯揺らぐ可能性があるものです。しかし多くのトランスジェンダーが自認するまでに、そして移行を決めるまでに長年の葛藤を経ており、一時の気分で性を変えるということは考えにくいのが現実です。
●社会からもたらされる生きづらさ
誤解や偏見は、往々にして差別につながります。SNSを中心に、「トランス女性が女性トイレに入ると、女性が危険にさらされる」という言説がはびこっていますが、これには根拠がありません。
トランス女性は、普通に女性として生きている人たちであり、犯罪をするために性別を移行したわけではありません。特定の人を、根拠がないまま危険だと決めつけることこそ、差別にほかならないでしょう。トランス女性もまた、暴力の被害を受けやすい立場にあることも、考慮する必要があります。
このような偏見があると、トランス女性もトランス男性も、外出先でトイレを使うのを躊躇するようになり、生活上の大きな困りごととなります。
社会の無理解と偏見は、トランスジェンダーにさまざまな生きづらさをもたらします。ホルモン療法や手術を望む人が、安心してアクセスできる医療機関が少なく、費用の負担がかなり大きいのも、そのひとつです。

メンタルヘルスにも課題が多く、日本で12〜34歳のLGBTQを対象にした調査では、約半数が自殺を考えたことがあり、約14%が自殺未遂をした経験があると回答しています。トランスジェンダーの若者もここに含まれています。米国の調査によると、トランスジェンダーの成人は一般の成人に比べて、自殺を考えた経験がおよそ7倍、自殺未遂がおよそ4倍、自傷行為がおよそ8倍と、深刻に高い傾向が報告されています***。
***U.S. Transgender Survey 2022
社会生活を営むうえでの大きな困難として、仕事に就くむずかしさもあげられます。面接で戸籍の性別と見た目の性別の違いを理由に落とされたり、職場での偏見やトイレ問題などで働きづらくなり退職したりといっことがあります。その結果、不安定な雇用に追いやられるのも、ひとつの傾向です。
* * *
トランスジェンダーの人にとって、性自認は「選ぶもの」でも「そうなりたいというワガママ」でもなく、「そうであるもの」です。それは、シスジェンダーの人にとって自身の性のあり方が「最初からそうだった」というのと同じです。私たちはみな、トランスジェンダーを含む多様な性のあり方を生きる一員です。そのかかわりを尊重へと向けるのか、それとも差別を広げてしまうのかは、一人ひとりの選択にかかっています。