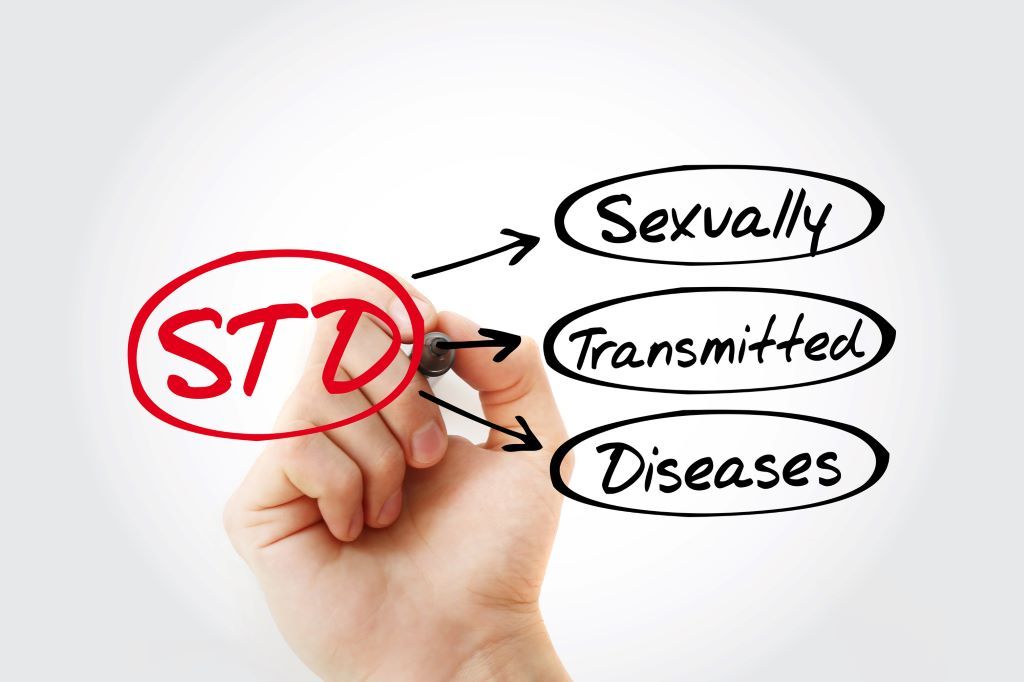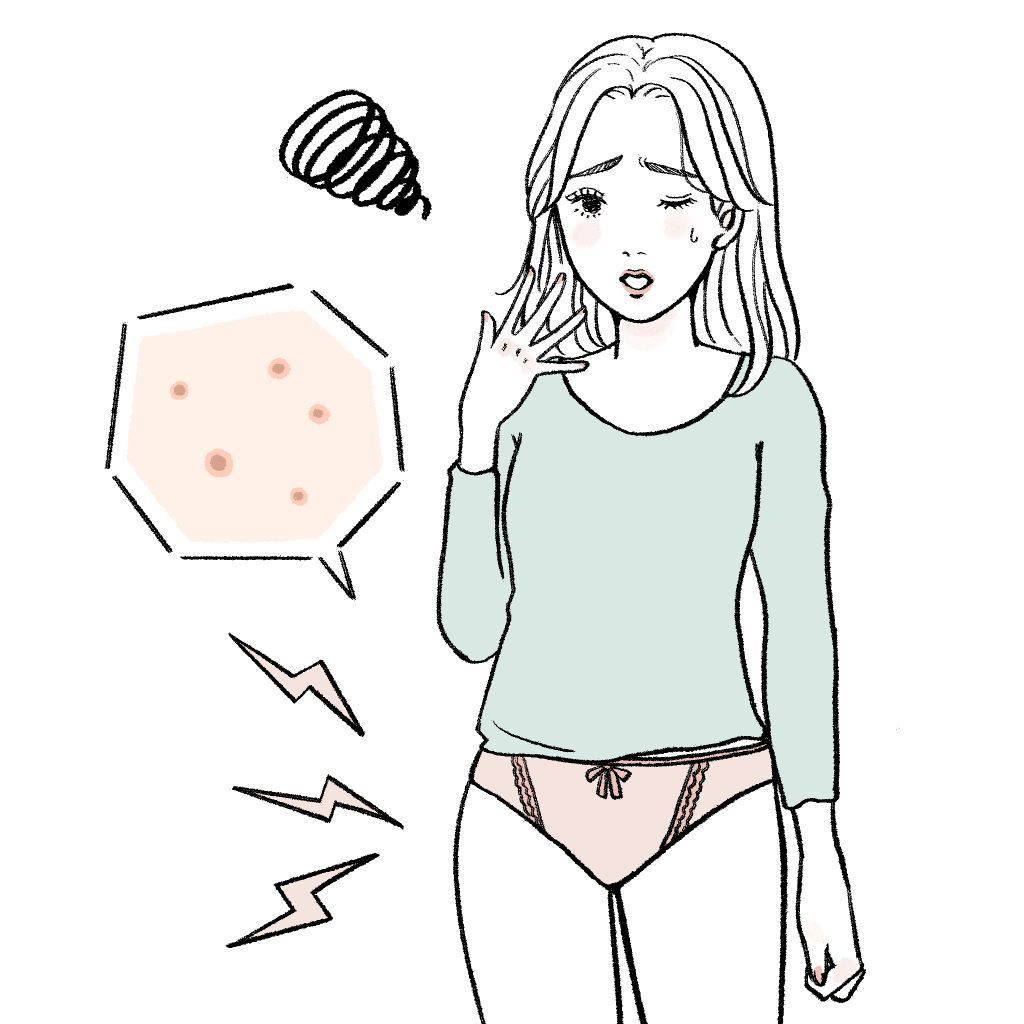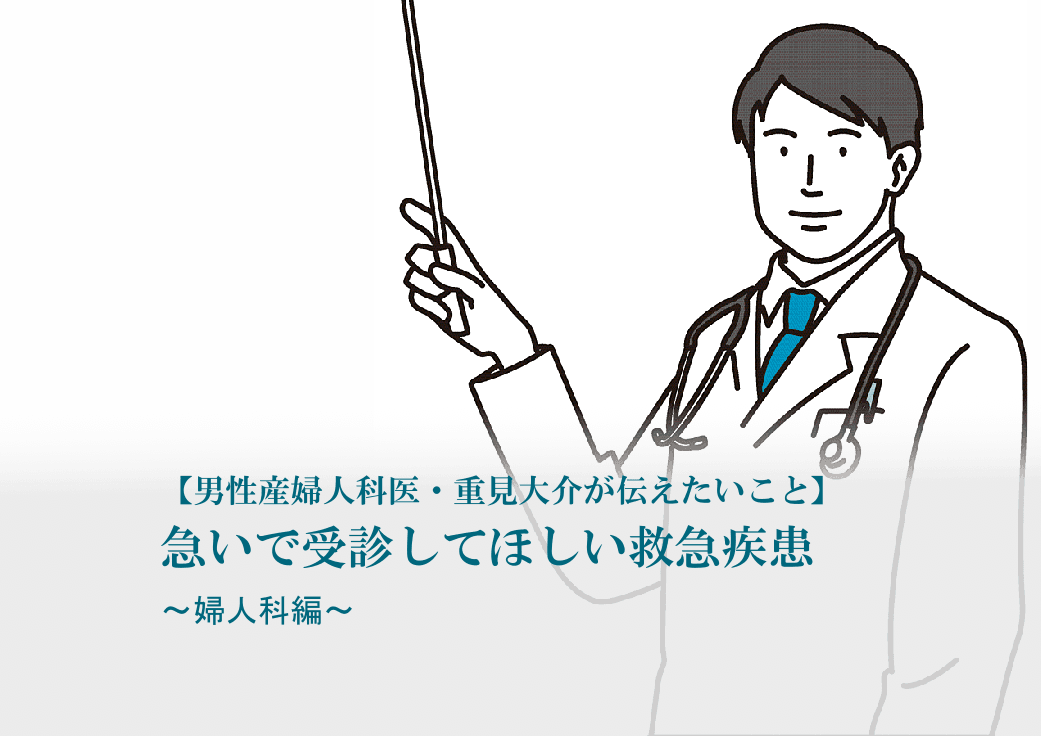クラミジアの男性症状とは?排尿痛・分泌物・無症状の見逃しサインと検査・治療法まとめ
クラミジア感染症は、性行為を通じてうつる性感染症のひとつで、日本でも最も多いとされる感染症です。特に10代後半から30代前半の若い世代での感染が多く、自覚症状が出ないことも少なくありません。そのため、気づかないまま感染を広げてしまったり、放置して重い合併症につながったりすることもあります。
前回は女性に関する情報を解説しましたが、今回は男性編です。女性編の記事はこちら。
クラミジアに感染した男性に起こる代表的な症状やサイン、検査・治療の方法、そして再発やパートナーとの感染を防ぐための注意点について、解説します。パートナーの健康を守るためにも、まずは正しい知識を持つことが大切です。
クラミジアとは?
クラミジアについて「聞いたことはあるけど、具体的にはよくわからない」という方も多いと思います。原因となる細菌や潜伏期間、そして性交渉だけでなくオーラルセックスやアナルセックスを通じても感染するこの病気について、基礎知識を整理します。
クラミジア感染症の基礎知識
クラミジア感染症は、クラミジア・トラコマチスという細菌が原因で起こる性感染症です。細菌といっても一般的な食中毒菌などとは違って、性行為を通じて尿道、咽頭(のど)、直腸といった粘膜に感染します。男性は尿道炎の形で現れることが多く、母子感染(出産時に産道を通じて赤ちゃんにうつる)も知られています。
感染してから症状が出るまでの潜伏期間は 1〜3週間ほど。さらにやっかいなのは、感染しても自覚症状がほとんどない人が多いことです。自分が感染していることに気づかず、パートナーへうつしてしまう可能性があります。20代の若年男性における初尿スクリーニング検査では、クラミジアの陽性率は4-9%とする報告もあります。
クラミジアは命に関わる病気ではありませんが、軽視して放置するのは危険です。不妊の原因となったり、パートナーの妊娠や、妊娠中のパートナーに感染すると赤ちゃんにも影響を与えたりするため、無症状でも感染している可能性があることを理解しておくこと、そして早めに気づいて治療することが大切になります。
感染経路は?
クラミジアの主な感染経路は、性交渉(腟性交)ですが、それだけではありません。オーラルセックス(口を使った性行為)やアナルセックス(肛門を使った性行為)でも感染することがあります。性器から口や肛門への感染もあれば、逆のパターンもあるため、性行為に関わる、あらゆる接触で感染の可能性があることを理解しておきましょう。
パートナーと「ピンポン感染」
「自分は症状がないから問題ない」と思い込んでいると、知らぬ間にパートナーにうつしてしまっていることもあります。男女ともに無症状のことが多く、パートナーが婦人科や泌尿器科で感染を指摘されて、初めて発覚するケースもあります。お互いに感染を繰り返してしまう「ピンポン感染」を防ぐためには、2人同時に検査・治療をしなくてはなりません。
クラミジアの主な男性症状|排尿痛・尿道のかゆみ・分泌物
男性のクラミジア感染は、尿道に症状が出てくるのが典型的なパターンです。排尿時の痛みや透明〜白濁した分泌物、かゆみなど、ちょっとした違和感を感じることがあります。とはいえ症状は軽く、ただの風邪や疲れと勘違いしてしまうことも。違和感を感じたら泌尿器科を受診しましょう。男性に起こる代表的な症状を具体的に見てみます。

排尿時の痛み・灼熱感・違和感
クラミジアに感染すると、まずあらわれやすいのが「排尿時の違和感」です。「尿道がチクチクする」「おしっこがしみる」といった表現をする方もいます。これは尿道(おしっこの通り道)に炎症が起きていることを意味しています。クラミジアは発熱したりといった病気らしい全身症状はないことが多いため、こうした違和感に気づいても見過ごされがちなのです。
尿道からの透明〜白濁した分泌物
もうひとつの特徴的な症状が「尿道から出る分泌物」です。透明〜白っぽい膿のような液体が見られることがあります。朝起きたときに下着に付いて気づく人も多いです。ただし、分泌物の量は多くないこともあるため、精液かな?と思って見過ごしてしまうことも。
尿道のかゆみや不快感の特徴
「かゆい」「ムズムズする」といった違和感も、感染初期に見られる症状です。痛みがないからといって放置してしまうと、菌が奥へと進み、より深刻な状態になることもあるので、ちょっとした異変を軽視しないようにしましょう。
感染が進行するとどうなる?重症化のサインとは
軽い違和感だけで放置してしまうと、炎症が広がると精巣上体(副睾丸)にまで到達することがあります。副睾丸炎による強い痛みや腫れ、不妊につながる精管閉塞、さらにHIVなどの性感染症にかかりやすくなるリスクも。ここでは「見逃してはいけない重症化のサイン」を紹介します。
精巣上体炎・副睾丸炎(陰嚢の腫れ・痛み)
クラミジアを治療しないでいると、菌が尿道から奥へ奥へと進んでいき、最終的に精巣の近くにある「精巣上体」という部分まで到達して炎症を起こします。これが精巣上体炎です。精巣上体は精巣(睾丸)の上にくっついている小さな器官のことで、精子を育てて蓄える、大切な場所です。クラミジアがここに炎症を起こすと、陰嚢(いんのう:睾丸が入っている袋)が腫れたり、強い痛みが出たりします。
クラミジア性精巣上体炎では症状は様々で比較的軽いものから高熱をきたすものまであります。例えば、発熱しても37℃台程度に留まるケースが多いです。
他の性感染症の同時感染リスクも
クラミジアに感染していると、粘膜が炎症を起こして傷ついている状態になり、他の性感染症に感染しやすくなることもわかっています。感染症同士が重なることで、症状や合併症が複雑化することもあるため注意が必要です。
クラミジアの検査方法は?|保険はきくの?
そもそも何科に行けば良い?
女性の場合、デリケートゾーンの悩みは産婦人科ですが、男性の場合は「泌尿器科」になります。医療機関によっては、性病科、メンズクリニックといった名前で診療をしているところもあります。
また、自治体によっては保健所で性感染症の検査を実施しているところもあります。クラミジア検査が含まれているかどうかは自治体によって異なります(例えば、東京都では新宿区の検査には含まれていますが、千代田区ではHIVのみが対象となり、クラミジアは含まれません)。この検査は無料・匿名で受けることができますが、検査実施日があらかじめ決められており、主に平日の検査予定日、特定の時間帯に、予約をしていく必要があります。
自分の好きな時に受けられるわけではありませんので、時間の都合がつけにくい方は、クリニックなどでの検査をおすすめします。

検査方法の種類(尿検査・尿道採取)
クラミジアの検査にはいくつか方法があります。最も一般的なのは尿検査で、核酸増幅検査(NAAT)という検査をします。初尿と言われる排尿の最初の尿を採取し、クラミジア菌の遺伝子を検出する方法です。精度が非常に高く、少量の菌でも見つけられます。
また、尿道から綿棒でぬぐう方法や、のどや肛門の検査には専用のスワブを使って検体を採取することもあります。昔は尿道に綿棒を入れる検査が主流でしたが、痛みや苦痛を伴うため、現在では尿検査が一般的になりました。
診察直前のトイレは控えるのがおすすめ。
泌尿器科の検査方法は、クリニックの設備や方針にもよります。
すぐに検査できる設備のあるところでは、先に性器の状態を確認し、亀頭の先端にペタッとスライドグラスをくっつけて検体をとり、検査をする場合もあります。
クラミジアを疑う場合には、採尿して尿をとり、検査するのが一般的です。このとき、初尿(最初の尿)に細菌が混ざってきますので、我慢できる範囲であれば、直前のお手洗いは行かないままでの受診がおすすめです。
無症状でも検査すべきなのは?
クラミジアに感染してから症状が出るまでの期間(潜伏期間)は、1〜3週間程度とされています。しかし、全く症状が出ないまま経過する人も多く、自分では気づかないうちに他人へ感染させてしまうことが少なくありません。症状がない場合でも、以下のようなときは検査を検討しましょう。
・パートナーが変わったとき
・パートナーに感染が見つかったとき(自分に症状がなくても保険が適用されます)
・性器に何らかの違和感があるとき
検査費用・保険適用の有無
医療機関で症状があり「診療上の必要性がある」と判断された場合、保険適用での検査が可能です。自己負担額は3割で、数千円程度が一般的です。一方、無症状で「念のため」の検査は自費扱いになることも多く、医療機関や検査内容によって費用が異なります(5,000〜10,000円程度が目安)。
また、保険のルール上、同じ病気で複数の部位の検査はできないことになっているため、性器の検査と、咽頭(のど)の検査は同時にすることができません。もし症状が出ていたり、感染を疑う行為があった場合は、耳鼻咽喉科に相談してみるのも一つの方法です。
クラミジアの治療方法と注意点|再発・治療中の性行為は?
主な治療は抗菌薬の内服
クラミジアの治療は、抗菌薬(抗生物質)を使った内服治療が基本です。数日〜2週間に渡り継続して飲むお薬で、中には1回の内服で済む薬もあります。服薬での治療が基本ですが、症状が重い場合や、内服薬が効きにくい場合には、点滴が行われることがあります。
薬の飲み方と注意点|飲み切ることが大切
症状がよくなったりして抗菌薬を途中でやめてしまうと、菌が残って再発するリスクがあります。たとえ症状が消えても、医師に処方された日数分は必ず飲み切るようにしてください。まれに吐き気や下痢、発疹といった副作用が出ることもありますが、我慢せず医師に相談しましょう。
治療期間中の性行為はNG!再感染の防止につとめよう
薬を飲んでいる期間、そして治療完了後もしばらくは性行為を控え、お互いに再検査を受けて陰性が確認できるまでは、性行為によって再感染したり、相手に感染を広げたりする可能性があるからです。治療を機に、パートナーとの感染対策についても話し合うことも大切です。
パートナーも一緒に治療を|再感染・ピンポン感染を防ぐために
カップルでの同時検査・治療が重要な理由
自分だけが治療しても、パートナーが未治療のままだと、再び感染してしまう「ピンポン感染」が起こりやすくなります。感染がわかったときは、必ずパートナーにも知らせ、2人そろって検査・治療を受けることが大切です。相手に伝えるのは勇気がいることかもしれませんが、お互いの体を将来を含めて守るためですので、きちんと伝え、一緒に治療するようにしましょう。
治療が終わったら再検査を
クラミジアは、治療後、3~4週間程度たってから再検査を行うことが推奨されています。特に症状がなかった場合でも、きちんと陰性化していることを確認するためです。また、再検査で陰性が確認されてから性行為を再開することで、再感染のリスクを減らすことができます。
パートナーへの伝え方・相談のしかた
もしクラミジアの診断を受けた場合、パートナーへの伝え方に悩む方も多いかもしれません。「一緒に検査を受けよう」と協力を求める形で話すと、相手も受け入れやすくなると思います。
むやみに問いただす姿勢ではなく、あくまで「あなたの健康を守りたい」というスタンスで臨むのがおすすめです。
男性ができるクラミジア予防法|今日から始める3つの対策
コンドームは正しく使う
コンドームの使用は、クラミジアを含む性感染症の予防に有効ですが、正しく使うことが前提で、100%予防できるわけではありません。「途中から着ける」「破れたまま続ける」などの誤った使い方では効果が十分ではありませんので、性行為の最初から最後まで正しく着用します。また、忘れがちなのが使用期限や保管状態。期限切れや保管状態が悪いと傷がついたりして本来の効果を発揮できません。おうちに在庫がある場合は定期的に確認して買い換えるのがおすすめです。
定期的な検査習慣を身につけておく
症状がなくても感染している可能性があるクラミジアだからこそ、定期的な検査で自分のことを知るのが大事になります。たとえば、パートナーが変わったタイミングなど、性交渉がある場合を目安にすると良いです。性感染症ドックを受診したり、自治体によっては保健所で無料で受けられる性感染症検査もあるので、うまく活用しましょう。
パートナーとオープンなコミュニケーションを
性感染症は、誰でもかかる可能性があります。普段から、パートナーと率直に話し合える関係を築くことが大事。

よくある質問(Q&A)|不安・再発・日常生活で気をつけること
一度かかったらもうかからない?
いいえ。一度クラミジアにかかったことがある人でも、治療後に再び感染することはあります。感染したからといって免疫ができるわけではないため、予防を続ける必要があります。
仕事・日常生活への影響はある?
治療はお薬を内服するだけですので、治療中でも、通常の仕事や日常生活は問題なく行えます。ただし、強い炎症や合併症がある場合は医師の指示に従って休養が必要なこともあります。インフルエンザやコロナ等と違い、性感染症は職場に伝える義務はありませんが、痛みがあるなど心配な場合は医療者に相談を。
再発や他の性病との違いは?
クラミジアは再感染が多い病気です。「再発」ではなく「再感染」であることが多いため、パートナーも含めた予防対策が必要です。また、クラミジアと症状が似た性感染症には淋菌感染症(淋病)なども。改めて別記事で解説しますが、自己判断せず、医療機関を受診して正確な診断を受けましょう。
【まとめ】クラミジアは「気づかないこと」が一番のリスク。だからこそ、知って・防いで・早めの相談を。
クラミジア感染症は、特に若い世代の男女に見られる性感染症でありながら、多くの感染者が「無症状」とされています。自覚のないまま放置すれば、パートナーへの感染はもちろん、ご自身の身体にも副睾丸炎など痛みを伴う深刻な影響が出ることがあります。
女性が感染した場合はもっと深刻で、将来の不妊につながったり、癒着によって下腹部痛を伴ったりしますので、パートナーを守る意味でも、早期発見、治療がとても大事です。crumiiでは女性のクラミジアについても詳しく解説しています。こちらの記事をどうぞ。
クラミジアはきちんと検査し、適切な治療を受ければ治る病気です。
大切なのは、
・少しでも違和感があれば、恥ずかしがらず医療機関に相談すること
・自覚症状がなくても検査を定期的に受けること
・パートナーと協力して治療し、再感染を防ぐこと
知らなかった、では済まされないこともあるからこそ、この記事をきっかけに理解を深め、ご自身とパートナーについて考える一助になれば幸いです。
【参考文献】
ねころんで読める性感染症 株式会社メディカ出版,2023
MSDマニュアル プロフェッショナル版
性感染症診断・治療ガイドライン2020 日本性感染症学会 株式会社診断と治療社,2020
性感染症診療マニュアル 達人の口伝編 学研プラス,2021