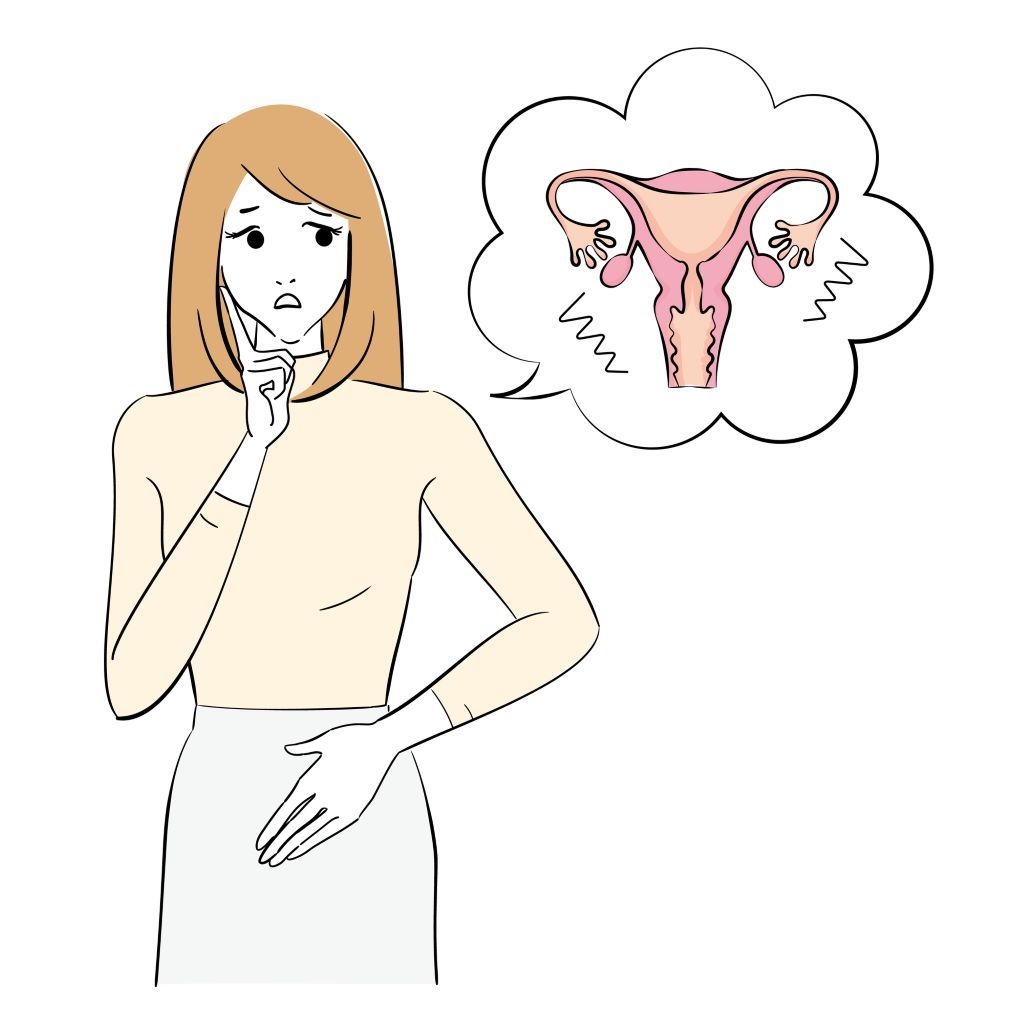女性のクラミジア症状と治療の完全ガイド|無症状でも不妊・妊娠合併症リスクに?
クラミジア感染症は、日本で最も多い性感染症(STD)のひとつです。特に女性の場合、感染しても自覚症状がないことが多く、「知らないうちに長期間放置」してしまうことがけっこうある感染症です。
放置すると、骨盤内に炎症が広がり不妊や異所性妊娠(子宮外妊娠)、妊娠中の合併症など、将来の妊娠や健康に深刻な影響を及ぼすことがあります。
本記事では、原因や症状、検査・治療の流れ、予防のために知っておきたいポイントを、専門的な内容も含めてわかりやすく解説します。
クラミジア感染症とは?女性が知っておきたい基礎知識
クラミジア感染症は「クラミジア・トラコマチス」という細菌によって起こる性感染症です。女性では主に子宮頸管(しきゅうけいかん)という子宮の入り口部分に感染し、そこから上の子宮や卵管に広がることがあります。感染部位は性器だけでなく、オーラルセックスによる咽頭(のど)や、アナルセックスによる直腸にも及ぶことがあります。
感染経路は大きく分けて3つ。
1. 性行為(腟性交)
2. オーラルセックス(のどへの感染)
3. 母子感染(妊婦が感染している場合、出産時に赤ちゃんの目や肺に感染)
潜伏期間(病原体が体内に入ってから症状が出るまでの期間)は1〜3週間程度で、その間の性交渉で症状が出ないまま相手に感染させてしまうこともあります。実際、女性では感染者の80〜90%が無症状とされており、気づかないうちに感染が進行することが大きな特徴です。
女性のクラミジア症状【部位別】
クラミジアは感染部位によって症状が異なります。性器だけでなく、咽頭(のど)や直腸にも感染し、それぞれ特徴的な症状があります。
性器症状
女性のクラミジア感染では、まず子宮頸管に炎症が起こります。典型的な症状はおりものの増加やにおいの変化、性行為後の軽い出血(接触出血)、そして下腹部の鈍い痛みです。炎症が卵管まで進むと、炎症が骨盤の腹膜にまで広がった骨盤内炎症性疾患となり、より強い下腹部痛や発熱を伴うことがあります。とはいえ、こうした症状が自覚症状として出るのは感染者全体の1〜2割程度にとどまり、多くは「いつの間にか進行」してしまいます。もし以下のような症状があった場合は、早めに産婦人科を受診して相談しましょう。
おりもの
通常と比べておりものが増えたり、黄色や緑色の濃い色になったり、悪臭がするようになる場合があります。
不正出血
性交時に痛みを感じたり出血を伴う、下腹部に鈍痛が起きたりといった症状もクラミジアの典型的な症状。また、生理以外のタイミングで不正出血がある場合も要注意です。生理が多少ずれる程度なら問題はありませんが、変な時期に不正出血がある場合は、他の病気の可能性もありますので、早めの受診がおすすめです。
咽頭(のど)症状
オーラルセックスによって咽頭に感染することがあります。ほとんどが無症状ですが、まれにのどの痛みや違和感、軽い発熱など、風邪に似た症状が出ることがあります。このため単なる咽頭炎と思ってしまい、クラミジアの検査を受けずに放置される例もあります。
直腸症状
アナルセックスや性器から直腸の粘膜への感染で起こります。こちらも無症状が多いですが、肛門周囲の違和感や分泌物、出血などがみられる場合があります。痔や軽い肛門炎と区別がつきにくいことがあり、検査が遅れることもあります。
クラミジア性結膜炎(目の感染)
まれに目に感染することもあり、充血や目やに、かゆみなど結膜炎の症状が現れます。放置すると目に悪影響を与えるため、症状が現れたらすぐに眼科を受診しましょう。
放置による女性の合併症
症状が軽くても油断は禁物です。治療せずに放置すると、症状がないまま炎症が子宮や卵管に広がって、不妊症や異所性妊娠(子宮外妊娠)の原因になることがあります。特に女性は、生殖器や妊娠に関わる健康被害が大きく、早期の発見と治療がかなり大事です。
骨盤内炎症性疾患(PID)は、クラミジアが子宮から卵管、さらに骨盤内全体へ広がることで起こる炎症です。発熱や強い下腹部痛、性交痛などが出ますが、慢性化すると痛みが軽くても炎症は進行してしまいます。
妊娠中に感染していると、流産や早産のリスクが高まるほか、分娩時に赤ちゃんに感染して結膜炎や肺炎を引き起こす「母子感染」の危険があります。特に肺炎は出生後数週間で発症し、長引く咳や呼吸障害を伴うため注意が必要で、出産前には、多くの施設でお母さんのクラミジアの検査を実施しています。
卵管に癒着や閉塞が起こると何がよくないの?
クラミジアの怖いところは、将来の妊娠に影響を及ぼすことがあるところです。
卵管は、排卵された卵子を子宮まで運び、精子と出会わせる重要な通り道です。クラミジア感染を放置すると、炎症が卵管に及び、内側の粘膜が損傷して癒着(組織がくっつくこと)や閉塞(ふさがること)が起きることがあります。
卵管が狭くなったり塞がったりすると、卵子と精子が出会えず、不妊症の原因になります。さらに、完全にふさがっていなくても通りが悪くなると、受精卵が子宮まで移動できず、途中で着床してしまう異所性妊娠(子宮外妊娠)のリスクが高まります。これは母体の命にも関わる緊急事態です。
卵管のダメージは、一度起こると元に戻すのが難しく、例えば異所性妊娠(子宮外妊娠)への手術をしても完全に機能が回復するとは限りません。そのため、症状がないからと放置せずに、早めの検査と治療で癒着を予防するのがとても大切なのです。
【用語解説】
・卵管癒着:炎症などで卵管の組織同士がくっつく状態。
・卵管閉塞:卵管の内部がふさがり、卵子や精子が通れなくなる状態。
・子宮外妊娠:受精卵が子宮以外(多くは卵管)に着床する異常妊娠のこと。異所性妊娠については、こちらの記事でも詳しく解説していますので合わせてどうぞ。
クラミジア検査の流れ【女性】
感染の有無を正確に知るには検査が必要です。女性が検査を受ける際には、内診台でおりものを採取し、検査するのが一般的です。医師が診察時に最近の性交渉について聞く場合があります。ちょっとプライベートな質問ですが、これは性感染症の疑いがあるかどうかなどを確認するための問診なので、できるだけ正直に答えましょう。
検査方法(核酸増幅検査)
女性のクラミジア検査は、核酸増幅検査(NAAT)という検査が主流です。これは内診でおりものを採取し、クラミジア菌の遺伝子を検出する方法で、精度が非常に高く、少量の菌でも見つけられます。検体は腟や子宮頸管からの分泌物、または尿で採取します。咽頭や直腸の感染が疑われる場合は、綿棒でその部位の分泌物を採取したり、ガラガラうがいをした液を採取したりして、同様に調べることができます。
潜伏期間と受診のタイミング
クラミジアには感染してから症状が出るまでに1〜3週間程度の潜伏期間があります。症状がある場合はもちろん、感染の心当たりがある場合(例えば、パートナーが診断されたなど)にも、早めに産婦人科を受診し、感染可能性のある箇所を申告して早めに検査を受けましょう。
内診台でおりもの採取
医療機関での検査は、診察台(内診台)で医師が採取する方法が一般的です。
抵抗感がある場合は自己採取キットを取り扱っている医療機関もあります。自己採取は自分で腟から綿棒を挿入して検体を取るため、プライバシーが保たれますが、咽頭や直腸の検査には対応していない場合があります。
うがい液を採取
咽頭に症状があったり、感染の心当たりがある場合は、咽頭の菌を採取します。生理食塩水を口に含み、ガラガラうがいを続けた後、吐き出した液を採取して検査します。
保険適用・自費の違いと費用目安
症状がある場合やパートナーが感染している場合は保険が適用され、3割負担で1,000〜3,000円程度です。一方、症状がなく任意で検査する場合は自費になり、医療機関では5,000〜10,000円程度、自己採取キットでは4,000〜8,000円程度が目安になります。
妊娠・分娩への影響と健診時のクラミジア検査
クラミジアは自覚症状が少ないまま進行することが多く、気づかずに妊娠を迎えてしまうことも珍しくありません。妊娠中のクラミジア感染は、母体だけでなく赤ちゃんにも深刻な影響を及ぼす可能性があるため要注意です。
出産時に赤ちゃんに感染することも
感染が続いたままだと、早産や低出生体重児のリスクが高まるほか、分娩時に産道を通る際、赤ちゃんに感染してしまうことがあります。これが原因で新生児が結膜炎や肺炎を起こすケースも報告されています。
きちんと治療すれば問題ない
そのため、日本では妊婦健診の一環として妊娠20週前後を目安にすべての妊婦さんにクラミジア検査が行われます。(この検査は公費でまかなわれます)感染が見つかった場合は、妊娠週数に応じた安全な抗菌薬で治療します。もし感染が見つかっても、妊婦さんが飲める薬も多くありますし、適切な治療を行えば妊娠や出産への影響を最小限に抑えることができます。
また、このような可能性があることを知っておき、妊娠中に性行為をする際は、必ず予防を意識しましょう。

治療方法と治療の注意点
クラミジア感染症は、抗菌薬(抗生物質)を一定期間服用することで治療します。
治療中は指示された日数・量を守ってきちんと飲みきることが大切です。症状が軽くても服薬を途中でやめると菌が残ってしまい、再発やパートナーへの感染の原因になります。治療後は3〜4週間後に再検査を行い、確実に菌が消えていることを確認します。
基本は服薬での治療ですが、症状が重い場合や、内服薬が効きにくい場合には、点滴による治療が行われることがあります。
また、クラミジアは性行為によって相互に感染し合うため、パートナーも同時に治療することが必須です。どちらか一方だけが治療しても、相手からまた感染する「ピンポン感染」が起こります。治療期間中は性行為を控え、お互いの治療完了を確認してから再開するようにしましょう。

女性ができるクラミジア予防法|今日から始める3つの習慣
治療で一度治っても、クラミジアは何度でも再感染します。再発を防ぐためには、日常生活での予防策が欠かせません。
コンドームを正しく使う
クラミジアの感染予防に有効なのはコンドームの正しい使用ですが、100%の予防はできません。それでも予防確率を高めるために、最初から最後まできちんと装着し、破損がないか確認しましょう。
定期的な検査のすすめ
症状がなくても実は感染している、というケースも多いため、定期的な性感染症検査がおすすめです。特にパートナーが変わった際には検査を受けることを習慣化しましょう。保健所の無料検査を利用できる地域もあります。
信頼できるパートナーとのコミュニケーション
性感染症についてはパートナーとも話し合い、お互いに検査を受けることで感染リスクを下げることができます。感染症に、未来に関わるリスクがあることをお互いに理解しておき、オープンなコミュニケーションができる信頼関係を築くことが大事です。
よくある質問Q&A【女性編】
Q1. ピルを服用していても感染しますか?
はい。ピルは避妊や月経周期の調整に有効ですが、性感染症の予防効果はありません。コンドームを併用しましょう。
Q2. 妊娠初期に感染がわかった場合はどうしたら良い?
妊娠中でも使用できる抗菌薬があります。放置すると流産や早産、新生児への感染リスクがあるため、早めに治療を受けてください。
Q3. 生理中でも検査はできますか?
できなくはないですが、出血が多い場合は検査精度が下がることがあります。クラミジアの感染は、一刻を争う事態になる病気ではありませんので、検査はタイミングを調整して、生理が終わった後に受けるのが無難です。
まとめ|無症状でも放置はNG、早めの検査・治療を
クラミジア感染症は、女性が感染すると自覚がないまま進行し、将来の妊娠、ひいては生まれてくる赤ちゃんに深刻な影響を与えることもある病気です。骨盤内炎症性疾患、不妊症、妊娠合併症、母子感染などのリスク予防には、早めの発見と治療が不可欠です。
・感染経路は腟性交、オーラル、アナル、母子感染
・無症状でも感染している可能性あり
・治療は抗菌薬の内服 + パートナーも同時に治療が基本
・再感染予防にはコンドームと定期検査を
症状がない=安心していいというわけではありません。症状があったり、少しでも心当たりがあれば、早めに受診し、検査を受けておきましょう。
【参考文献】
病気がみえる 婦人科
今日の臨床サポート クラミジア感染症(婦人科),エルゼビア