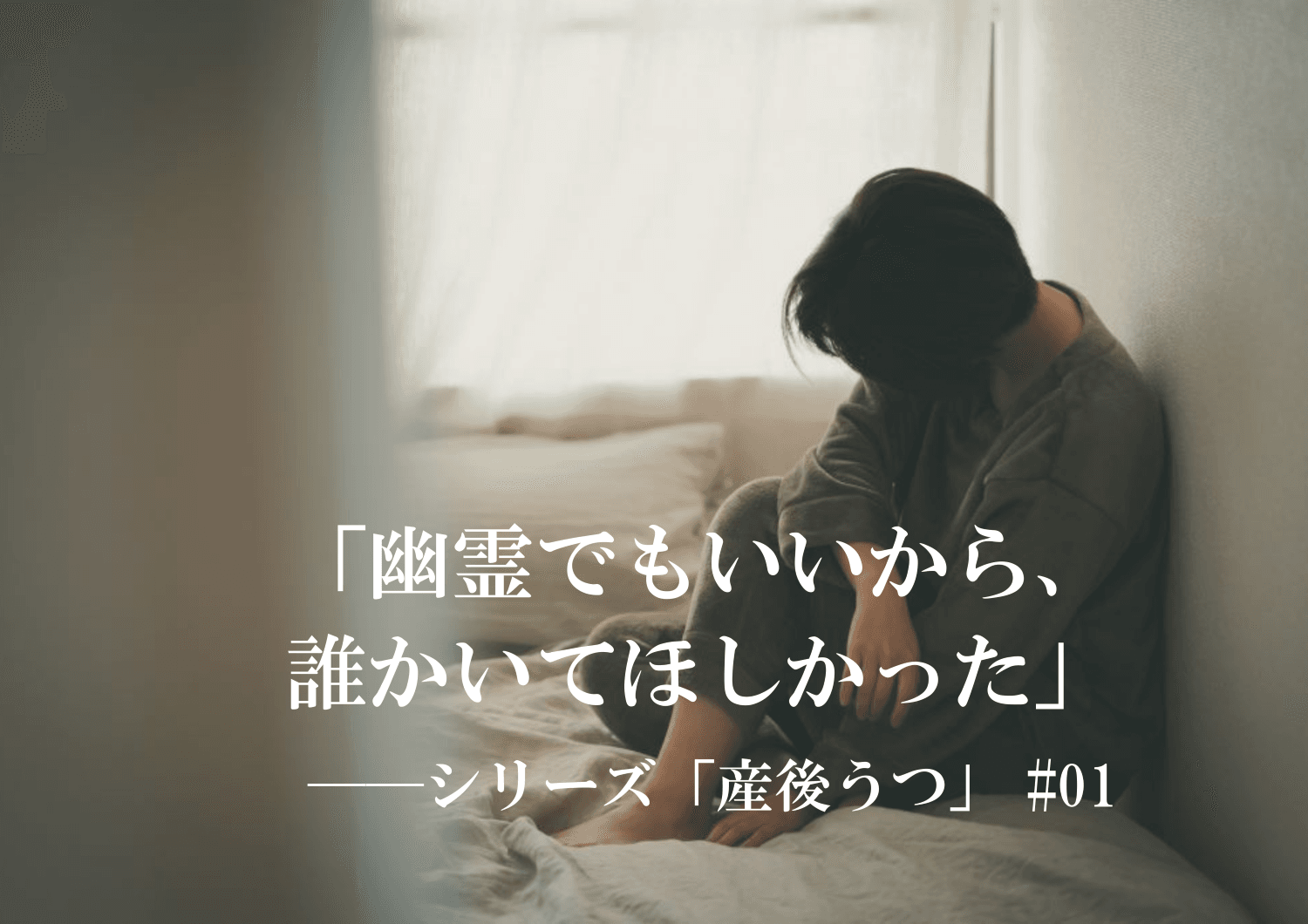シリーズ「産後うつ」 #02
周囲の気づきと「つながり」が鍵。産後うつから回復への道筋
ある調査※によると、出産経験のある女性の9割以上が「産後うつ」という言葉を認知しています。これほど多くの人が知っているのに、なぜ、いまだに多くの母親が孤立してしまうのでしょうか。それは、私たちが「産後うつ」という言葉は知っていても、その具体的な対処法までは理解していないからかもしれません。今回は、実際に産後うつを経験された熊田梨恵さんの体験談と専門的な知見を基に、本人と周囲の人々ができる具体的な対策について詳しく説明します。
(この記事は全3回の第2回目です。第1回を読む)
※ 「出産後の体調」に関する定点調査/子ねくとラボ(運営:株式会社明日香/調査期間:2025年3月5日〜同年3月5日)
「自分の弱さのせいじゃない」気付きが治療への第一歩
実は、産後うつを抱えている本人が「自分が産後うつであること」に気づいていないケースは少なくありません。前回の記事でも触れたように、熊田さんは産後うつになった要因の一つとして、「受診の遅れ」を挙げました。「これは単に私のメンタルが弱いだけだ」「育児が初めてで分からない、自分が弱いからだ」という強い思い込みが、彼女を病院から遠ざけていたと振り返ります。
このような思い込みから受診が遅れるのは、残念ながらよくあることです。多くの女性が月経のトラブルで経験するように、自分のつらさが客観的にどの程度のものなのか、他人と比較できない苦しみがあります。「この辛さで病院に行っていいのだろうか」「『お母さんなんだから頑張って』と言われて終わりなのではないか」。そんな不安が、医療へのアクセスを阻む大きな壁となります。
だからこそ、もし本人が気づけずに症状が進んでしまった場合は、まず周囲が「それはあなたの弱さのせいではなく、治療が必要な状態かもしれないよ」と、本人に気づかせてあげることが必要になります。
東京から駆けつけた友人を見て、事の重大さを認識
熊田さんが産後うつの深刻さを自覚したのも、周囲の人の行動がきっかけでした。
「子どもが5カ月くらいの時に夫の実家で不幸があり、私も子連れで遠方にある夫の実家に行くことになりました。そこで葬儀やらなんだかんだをこなしている最中に、私が倒れてしまったんです。そのことを友人にメッセージすると、心配して東京から夫の実家まで、ご家族も一緒に車を飛ばして駆けつけてくれたんです」
「あなたが壊れてしまう」と、東京から来てくれた知人の様子を見て、「他人が自分のためにそこまでしてくれるほど、自分は深刻な状態なのだ」と気づかされたことが、熊田さんを治療へと向かわせる大きな一歩となりました。
その後、産後ケアを行う医療機関で「産後うつ」と診断を受け、熊田さんはようやく回復への道筋を歩み始めたのです。
熊田さんが歩んだ回復のプロセス
療養のため、熊田さんが選んだ場所は、実家でした。ご両親がそれぞれ、認知症とパーキンソン病を患っていたことから、実家で過ごすことを避けていました。しかし、実際に暮らしてみると、誰かがそばにいてくれるだけで孤独感が和らぎ、安心して過ごすことができたといいます。
「母は認知症でしたが、子どもがいるとむしろ元気になったようで面倒を見てくれましたし、父もできる限りのことをしてくれました。誰かがそばにいてくれるだけで、気持ちが落ち着きました」
熊田さんの夫も育児休業を取り、一時的に実家で一緒に過ごすなど、家族のサポートを得られたことが回復に大きく寄与しました。そして約1年半後、再び夫、子どもと3人での生活に戻ることができました。当時を振り返って、熊田さんはこう話します。
「自分の状況を客観的に見つめられるようになってはじめて、私は子育ての困難さだけでなく、自分自身の未解決な問題も抱えていたことに気がつきました。療養中には、自分自身とたくさん向き合い、問題の解決に努めました。そのことも、産後うつを和らげる助けになったと思います」
その後、産後うつから回復した熊田さんは、「この経験を世の中に広めなくてはいけない」という使命感から、専門家へ取材し、記事の執筆を開始しました。
【本人にできること】産後うつへの備えと対策
熊田さんが専門家への取材やご自身の経験を経て学んだ、産後うつの対策を教えてくれました。まずは、女性が自分で行える対策を紹介します。
相談相手のネットワークを築く
「妊娠・出産という段階になった時に相談できる相手を一人でも多くイメージし、さまざまな繋がりを増やし、相談相手を事前に見つけておくことが重要です。専門的な相談ができる助産師や保健師、医療機関の相談窓口などのほか、気軽に愚痴を言える相手、緊急時に頼れる相手などを探しておきましょう。
加えて、行政や民間の子育てサービスについても、できるだけ事前に調べておきましょう。産後、心身の調子が優れなくなってからでは、そうした情報を検索することもままならない可能性があります。あらかじめ備えておくことが大切です」
助けを求めるスキルを意識する
「つらい時に『つらい』『助けて』と周囲に相談できることは、産後うつを悪化させないために大切なことです。『疲れた』『不安』『助けてほしい』などと感じたら、周囲の人に、素直に伝えましょう。我慢せず、できるだけ早い段階で伝えることが肝心です。その際に、具体的にどう助けてもらいたいのかを伝えておきましょう。例えば『買い物を頼みたい』のか、『数時間子どもを見てほしい』のかがわかれば、具体的な支え方がわかるので、スムーズなサポートにつながるはずです」
自分の感情や状況を客観視する
「私自身、長年カウンセリングなどを通じて、自分の感情や状況を客観的に見る『メタ認知』のトレーニングをしてきました。つらい時に自分の感情を日記に書くと、第三者の視点で自分と向き合えるようになります。
文章を書くのが苦手な人には、スマホでAIと会話するのも良い方法です。 医療の世界では、AIを活用した患者向けのツールがすでに実用化されています。 医師や看護師には遠慮してしまうような本音でも、AI相手なら気兼ねなく話せますから。 AIとの会話は文字として記録に残るので、その履歴を読み返すこと自体が、自分の状態を客観視し、理解を深めることにつながるはずです」
【周囲ができること】パートナーや家族による支援
続いて、パートナーや周囲の人ができる支援についても伺いました。

育児を「自分ごと」として捉える
「何より大切なのは、パートナーが育児を“自分ごと”として捉え、一緒に向き合ってくれることです。初めての育児に戸惑うのは、母親も父親も同じです。母親だからといって、特別な力があるわけではありません。わからないなりに必死で取り組んでいることを理解し、同じ当事者として、主体的に関わってくれることが、一番の支えになります」
家事は「手伝う」ではなく「分担する」意識で
「『手伝う』という言葉だと、どうしても『本来は妻の仕事』というニュアンスが生まれてしまいます。そうではなく、食事の支度や掃除といった一つひとつの家事を、夫婦二人のプロジェクトとして責任感を持って関わってもらえると、母親は『一人で戦っているわけではない』と感じることができます」
母親の休息時間を確保する
「例えば、『毎週〇曜日のこの時間は、自分が子どもを見るから、自由にしていいよ』というように、パートナーが主体的に母親の『休み』をスケジュールに組み込んでくれるだけで、母親は精神的に大きく救われます。その休息が、結果的に家族全体の穏やかな時間へとつながっていくはずです」
共感とアドバイスの使い分け
「多くの場合、当事者は『正しい答え』が欲しいのではなく、『このつらさを分かってもらえた』という安心感を求めています。悩みを聞くと、つい解決策を提案したくなってしまうかもしれませんが、まずは『大変だね』と、ただ話を聞いて共感してくれることが、何よりも心強い支えになります。一緒に悩み、同じ立場に立ってくれる、その姿勢だけで孤独感はまったく違うんです」
医療者への橋渡し役になる
「私自身がそうだったように、渦中にいる本人は自分の状態の深刻さに気づけないことが多いんです。だからこそ、最も近くにいるパートナーが異変に気づき、『一緒に話を聞きに行ってみない?』と専門家への橋渡し役になってくれることが、何よりの支えになります。その一歩が、大切な人を守る、誰にも代わることのできない大きな力になるのです」
大切なのは、多様な支援の「選択肢」を用意すること
産後ケアというと、母親が一時的に休んだり、非日常的な体験をしたりすることばかりが注目されがちです。しかし、それだけでは「本質的な孤立感の解消」にはつながらない、という指摘があります。熊田さん自身、「保育園入園後も育児のつらさは続き、限界を感じた」と語っており 、その言葉は、支援が一時的なものであってはならないことを物語っています。
彼女は、理想の支援の形を「一本の太い糸ではなく、たくさんの細い糸」と表現します 。
一つの完璧な制度に頼るのではなく、その時々の自分に合った多様な選択肢の中からサポートを選べる社会環境を整えること。それが、これからの産後ケアが目指すべき姿なのかもしれません。
次回の記事では、これまでの内容を総括し、専門医のコメントも交えながら、産後うつに対する総合的な理解を深めていきます。
※この記事は、産後うつの当事者である熊田梨恵さんへのインタビューを基に作成されました。支援方法には個人差があります。深刻な症状がある場合は、必ず専門医にご相談ください。
【参考文献】
・” 「出産後の体調」に関する定点調査” 子ねくとラボ(運営:株式会社明日香/調査期間:2025年3月5日〜同年3月5日), (参照 2025-06-15)
〈取材協力者プロフィール〉
熊田梨恵(くまだ・りえ)
NPO法人パブリックプレス代表理事。2015年に第一子を出産後、産後うつを経験。これをきっかけに自身の抱えていた心の傷と向き合い、現在は大阪で女性向け自助グループ運営。トラウマケアのための一般向け講座も行う。ふだんは医療ライター。著書に『救児の人々』『胃ろうとシュークリーム』など。
山本尚恵
医療ライター。東京都出身。PR会社、マーケティングリサーチ会社、モバイルコンテンツ制作会社を経て、2009年8月より独立。各種Webメディアや雑誌、書籍にて記事を執筆するうち、医療分野に興味を持ち、医療と医療情報の発信リテラシーを学び、医療ライターに。得意分野はウイメンズヘルス全般と漢方薬。趣味は野球観戦。好きな山田は山田哲人、好きな燕はつば九郎なヤクルトスワローズファン。左投げ左打ち。阿波踊りが特技。