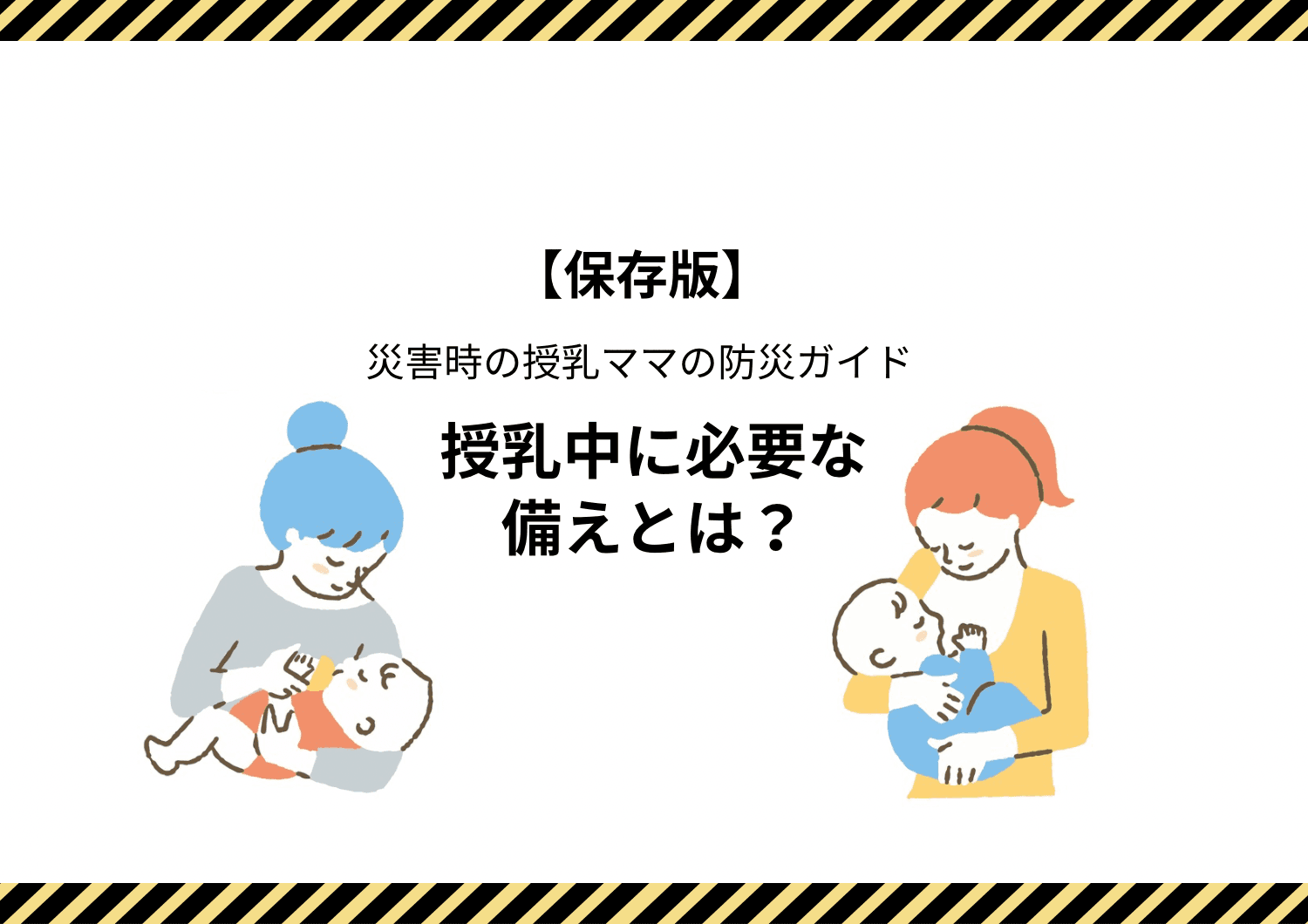【保存版】災害時の妊婦と授乳ママの防災ガイド|妊娠中に必要な備えとは?
9/1は防災の日。これまで、女性の防災対策についても特集してきましたが、平時とは違う妊婦さんや授乳婦さんも、普段から必要なものが多すぎて、あまり「備え」に対するイメージがつきにくいかもしれません。
「もし妊娠中に停電や断水になったら?」「赤ちゃんの授乳はどうすればいいの?」──そんな不安に、産婦人科の現場からお答えします。災害時は「普段どおり」が最優先。避難所での過ごし方の注意点から、妊婦さんにおすすめの防災グッズまで解説してみました。
妊婦さんの災害対策|体調管理と合併症予防
妊娠中は病気ではありませんが、お腹で赤ちゃんを育てるために、さまざまな体の変化を引き起こします。味覚や嗅覚が変わって好きだったものが食べられなくなったり、赤ちゃんが大きくなると膀胱が圧迫されて頻尿になったり、息切れ、貧血などにもなりやすくなったりします。
ただでさえ変化の大きい妊娠中の心と体。災害のショックや避難生活によって、精神的ストレスにつながってしまうことも少なからずあります。避難生活をすることになった場合には、自分の心と体の変化を注意深く観察しておきましょう。母子手帳や健診結果、常用薬などはすぐ持ち出せるようまとめておき、避難先では「無理をしない」「助けを借りる」のが大事です。
妊娠中の避難所生活で気をつけた方が良い合併症とは
妊娠中は血栓症になりやすい
避難生活で意識しておきたいのが、静脈血栓塞栓症。いわゆる「エコノミークラス症候群」です。長時間の同じ姿勢や脱水で、脚の静脈に血の塊(血栓)ができ、肺に詰まると危険な状態を起こすこともある病気です。妊娠中・産後の体は血栓ができやすく、長距離フライトなどで推奨されているのと同じ対策を心がけましょう。
災害時は、やむを得ず車内泊などの必要に迫られることもあります。こまめな水分補給・足の曲げ伸ばし、散歩など、ふくらはぎの運動を意識すること、就寝時に足を少し高くしておくことなどが有効とされています。締め付けの強い服装を避け、できれば弾性(着圧)ストッキングを活用しましょう。胸痛や片脚の腫れ・赤み・痛みが出たら早めに相談を。

栄養面の細かいことは気にせず、食べられるものを
食事・水分・体温管理は「お母さんの体を守る栄養」の視点で。温かい飲み物、エネルギー源、たんぱく質源を少しずつでも確保し、十分に休息をとって無理をしないのがコツです。
避難所でよく配られるパンやおにぎりは、炭水化物が多めでたんぱく質やビタミン、ミネラル、食物繊維などが不足しがち。とはいえ、被災中の状況では、何か食べられるだけで、生きているだけでえらい! 細かいことは気にせずに、目の前にある食事を大切にいただきましょう。できることといえば、サプリをあらかじめ防災グッズに入れておくなど。不足しがちなビタミンなどの栄養を栄養補助食品で補う工夫も良いですね。
メンタルのケアが最優先!!
妊娠中や産後、授乳中は誰しも、ホルモンの変化もあって感情が不安定になるもの。そこへ災害に見舞われたとなれば動揺するのも無理はありません。強い恐怖や気分の落ち込みを感じたら、女性の相談窓口、助産師や保健師・ボランティアへ早めに相談を。

医療機関を受診した方が良い兆候ってある?
インフラが断絶されたり、避難所での生活を余儀なくされると、お互いに気を遣って不調を言い出しづらくなるかもしれません。ですが、もし以下のような兆候があれば、危険なサインかもしれないので、必ず申し出て、医療機関へ連絡・受診をしてください。
1. 性器出血があった
2. 破水感
3. 強い腹痛やお腹の張りが続く
4. 胎動が急になくなった
5. 頭痛や目がチカチカする
妊婦さん・授乳婦さんは申告を|急な分娩に備える
必要な医療にきちんとつながるために
発災直後は、助けが必要な人から順に支援が届くよう「誰に何が必要か」を可視化する作業が最優先で進みます。避難所では避難者名簿(登録票)が作られ、氏名・生年月日・性別・住所に加えて、支援の要否や健康状態など個別のニーズが記録されます。
妊婦さんや授乳中の方、乳幼児を抱えるご家庭は「要配慮者」として配慮の対象に位置づけられており、災害時の母子保健マニュアルでも、妊産婦の情報共有と早期対応が推奨されています。
名簿に記載されることで、授乳・休養スペースの確保、物資配布の優先、必要に応じ福祉避難所への移動といった判断につながるので、最初の受付で、遠慮せず「妊娠○週です/授乳中です」とはっきり伝えましょう。
専門家が大集結。災害時のお産を支える仕組みとは?
避難中に心配なのは、設備のないところで急にお産が始まってしまうことです。地域の分娩を支える基幹病院では、災害時にも医療を維持するために、停電時の自家発電、断水時の貯水設備、医療ガスの確保などをはじめとした様々な対策がとられています。
あまり一般の人には知られていませんが、自治体、小児周産期リエゾンの連携もそのひとつ。発災時には、都道府県が「災害時小児周産期リエゾン」という専門調整員を配置し、災害時の妊産婦・新生児への医療提供を調整する仕組みになっています。
リエゾンは東日本大震災や熊本地震の際の事例を教訓に生まれた、都道府県の災害対策本部に参集される組織で、司令塔として情報収集や搬送の調整をする役割を担います。
地域の産婦人科医によって妊産婦の安否や状況などを確認するポータルサイトのような仕組みも作られています。これは医療従事者のみがアクセスできるもので、出産間近の妊婦さんが医療機関のないエリアで孤立したりすることのないように状況を把握したり、どの医療機関がどの程度お産の受け入れができる状況かを把握したりするのに役立てられます。
| 妊婦さんにおすすめしたい平時の備え | |
|---|---|
| (1) | かかりつけ、分娩先に非常時の対応を確認しておく。 住んでいる地域の「災害拠点病院」「周産期医療センター」の場所と連絡先は必ず把握を。 |
| (2) | 母子手帳・健診結果は「紙+スマホ」の二重保存を。 アレルギーや常備薬、緊急連絡先など記載事項は漏れのないように記入しておく。 いざという時の連絡先は事前に把握しておくのが大切。 |

災害時の持ち出しチェックリスト【妊婦さん編】
母子手帳は必ず。臨月に入ったら早めに入院バッグの準備を
妊婦さんは、経過がわかる母子手帳、検査の結果などを常に携帯しておきます。万が一に備え、携帯で撮った写真も保存を。場合によっては、かかりつけでない病院にかかることも考え、健康保険証は常に携帯するようにしておきます。
臨月に入ったら、いわゆる「入院バッグ」の準備は早めにしておきます。これは、パジャマなどのお泊まり用グッズに加えて、お母さん用の産褥ショーツ、赤ちゃんの退院時に着て帰るためのベビードレスやおくるみ、授乳ブラなど、産後に必要なものを揃えたバッグのことです。大きめのマザーズバッグやトートバッグなどに、必要なものをそろえ、準備しておきましょう。万が一、避難しなければいけなくなった時には、入院バッグも持ち出しましょう。
・母子健康手帳(写真やスクリーンショットなど、データでの保存も併用)
・健診結果の写し
・処方薬
・健康保険証
・ナプキン
・着圧ストッキングなど(むくみ防止)
・飲料水・軽食
・入院バッグ(産褥ショーツ、赤ちゃんのおくるみなどを入れたバッグ)
まとめ
災害は、いつどこで起こるかわかりません。妊婦さんや授乳中のお母さんは、妊娠やお産で体や心の変化があるうえに、赤ちゃんの命を守る責任を背負っているからこそ、災害に対する不安も大きくなると思います。
今回ご紹介したように、妊娠中は血栓症や高血圧症候群など、避難生活の環境によってリスクが高まる合併症があります。母子手帳や健診記録、常用薬を改めてまとめておくこと、最低限の備えを確保しておくことで、ひとつ不安を減らせます。
「着の身着のまま」で避難せざるを得ない状況も想定しながら、普段から備えておくことが大切。そして、避難所では遠慮せずに「妊娠中です」「授乳中です」と申し出てください。
災害は止められませんが、今からできることを少しずつ。この記事が、赤ちゃんとお母さんの防災を考えるきっかけになれたら嬉しいです。
【参考文献】
妊産婦を守る情報共有マニュアル 厚生労働省
エコノミークラス症候群の予防のために 厚生労働省
あかちゃんとママを守る防災ノート
厚生労働省 避難所等で生活している妊産婦、乳幼児の支援のポイント