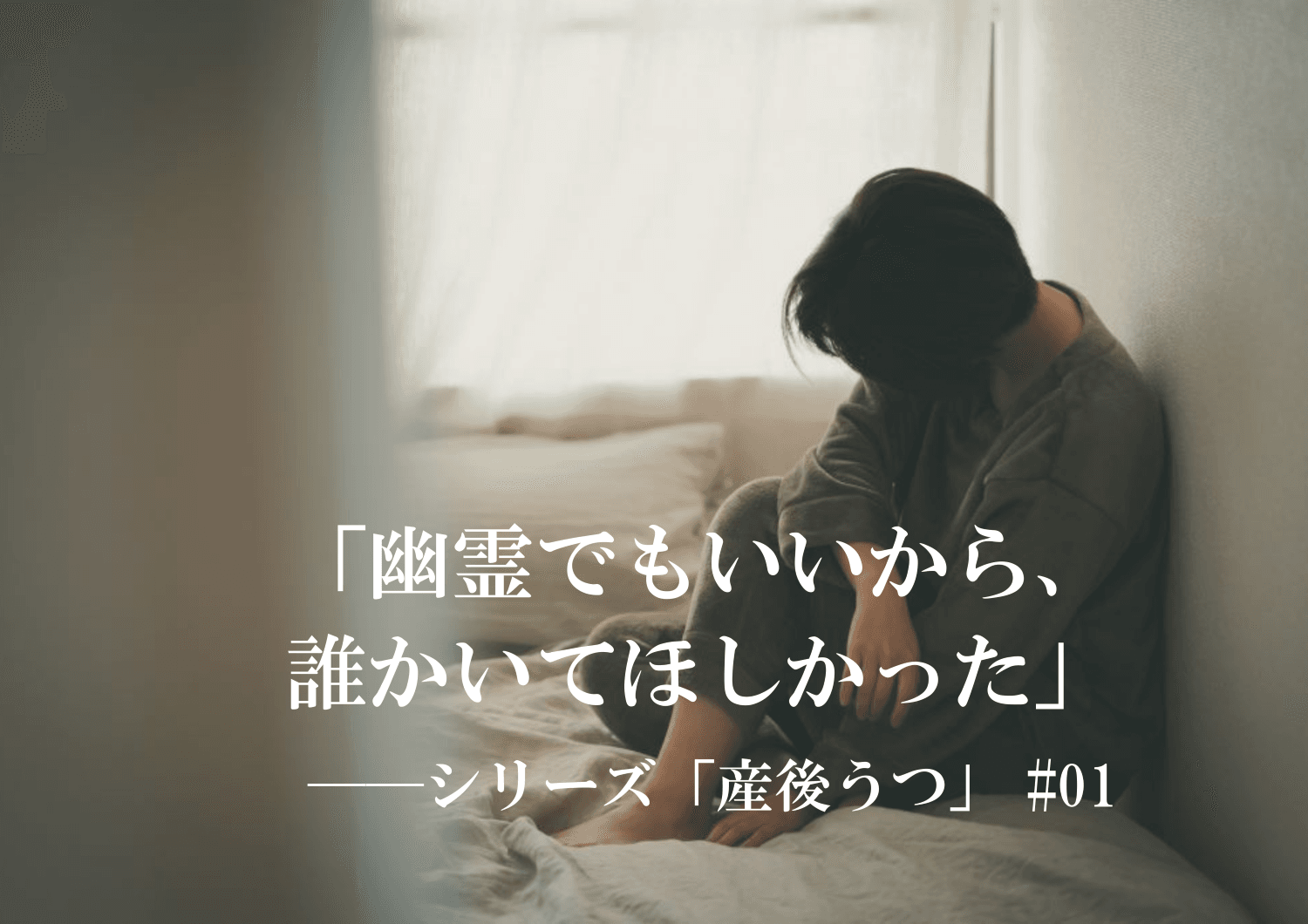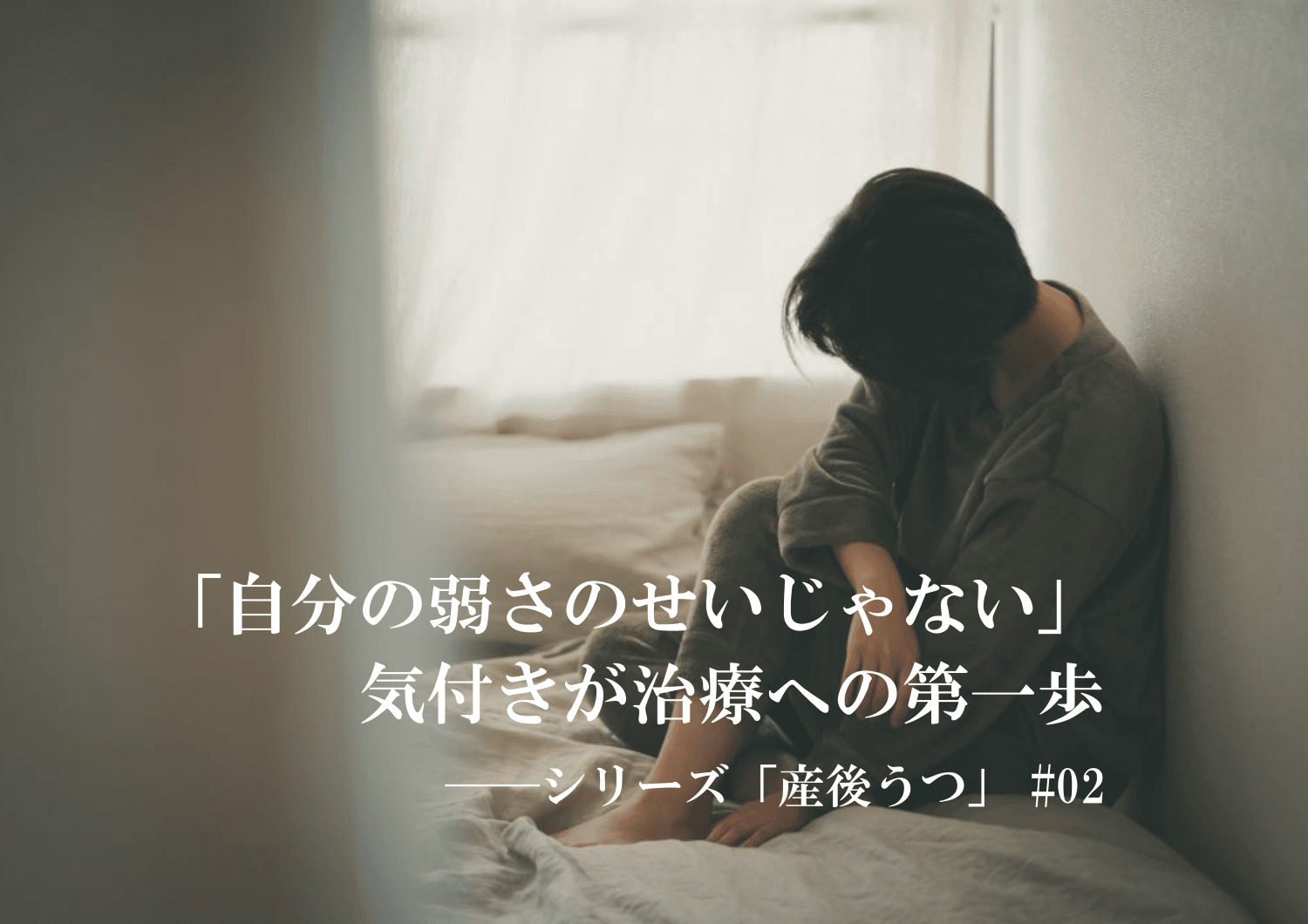シリーズ「産後うつ」 #03
産婦人科医が語る産後うつの真実:「誰にでも起こりうる」ことを理解し、社会全体で支える
産後うつは「10人に1人」が経験する身近な心の不調でありながら、いまだに多くの誤解に包まれています。「母親の甘え」「気持ちの問題」といった偏見が、苦しむ女性たちをさらに孤立させているのが現状です。この記事では、これまでお伝えしてきた熊田梨恵さんの体験談を踏まえ、産婦人科医・宋美玄先生監修のもと、産後うつの医学的な側面から社会的支援まで、総合的な理解を深めていきます。
(この記事は全3回の第3回目・最終回です。第1回目、第2回目を読む)
産後うつの医学的メカニズム
産後うつは決して「気の持ちよう」で片付けられる問題ではありません。その背景には、出産という劇的な体験に伴う、明確な身体の変化が存在します。そして、それが心にも影響を与えることがあるのです。
妊娠中に大量に分泌されていた2つの女性ホルモン、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)は、出産を終えると、まるでジェットコースターのように急激に低下します。ホルモンの急激な変動は、脳内の神経伝達物質のバランスにも大きな影響を及ぼします。その結果、熊田さんが体験したような「体が鉛のように重い」「霧がかかったように考えられない」といった症状が現れることがあるのです。
さらに、精神を安定させるのに欠かせない「セロトニン」や、意欲に関わるドーパミンといった神経伝達物質も低下することで、ネガティブな感情の高まりや、孤独を感じることが増え、うつ傾向がみられるようになることがあります。
「産後のホルモンの変動は、個人の意思や努力でコントロールできるものではありません。高熱で動けない人に『気合いが足りない』と言うのが的外れであるのと同じように、産後うつの症状を『怠けている』『甘えている』と捉えるのは、医学的に見て適切ではありません」 (産婦人科医・宋美玄先生)
知っておきたい「マタニティ・ブルーズ」と「産後うつ」の違い
産後の心の不調を理解する上で、まず大切なのが、産後うつとマタニティ・ブルーズの状態を区別することです。それぞれの特徴をあらためてまとめました。
マタニティ・ブルーズ
産後数日から2週間以内に見られる、一時的な気分の落ち込みや涙もろさなどを指します。多くの産婦が経験する生理的な変化であり、多くは自然に回復していきます。
産後うつ
以下に示すような症状が2週間以上続く場合は、「産後うつ」という治療が必要な病気の可能性があります。
【「産後うつ」を疑う心のセルフチェック】
・うまく笑えず、「楽しい」「おもしろい」といった感情を感じない
・何かを楽しみにすることがない
・失敗したり、物事がうまくいかなかったりした時、自分を不必要に責めた
・特に理由もないのに不安や心配な気持ちになることがある
・なぜだかわからないが、恐怖を感じることがある
・やらなければならないことがたくさんあって、つらい
・よく眠れない日が続いている
・わけもなく悲しくなったり、惨めになったりする
・自分を不幸に感じて、涙が出る
・自分なんでいなくなればいい、傷つけばいいという考えが浮かぶ
特に、「子どもや自分を傷つけてしまうのではないか」という考えが繰り返し浮かぶのは、産後うつの重篤な症状の一つといえます。すぐに産婦人科を受診し、専門医に相談してください。日本では産婦の約7人に1人に産後うつの傾向が見られるといわれています。
産後うつの治療法は?
産後うつと診断された場合、主な治療法には、十分な休養、カウンセリングなどの精神療法、そして抗うつ薬などによる薬物療法があります。
「授乳中の服薬を心配される方も多いですが、母乳への移行が少なく安全に使える薬剤も開発されています。治療を担当する医師や薬剤師とよく相談して、アドバイスをもらうとよいでしょう。
医療につながることができ、サポートが受けられれば、多くの場合、産後うつは改善できます。熊田さんが『起き上がることもできない』状態から回復できたのも、周囲の気づきによって適切な医療につながり、継続的なサポートを受けられたからといえるでしょう。諦めずに治療していきましょう」(宋美玄先生)
「もしも」に備える、予防的アプローチ
産後うつが心配な場合は、「エディンバラ産後うつ病質問票(EPDS)」という、産後うつのスクリーニング(早期発見の検査)のための質問票などを用いて、定期的に心の状態をチェックすると、産後うつの早期発見につながりやすいかもしれません。
エディンバラ産後うつ病質問票は、厚生労働省のサイトにも公開されていて、インターネットで検索すればすぐに見つかるはずです。あまり神経質になるのもよくないですが、質問票を見て、「こういう兆候があれば要注意だ」と知ることは大切です。
また、2021年から全国の市町村で制度化された「産後ケア事業」の活用も有効です。助産師など専門家のケアを受けられるデイサービス型、宿泊型、訪問型といったサービスがあります。こうした選択肢があることを妊娠中から知り、いざという時に利用できるよう準備しておくことが、未来の自分を助けることにつながります。
社会全体で取り組むべき産後うつ対策
産後うつは、医療の問題だけでなく、社会全体で取り組むべき課題です。産後うつに対応できる専門医療機関の不足や、精神科と産婦人科の連携体制の強化といった医療体制の整備。産後ケアサービスへの補助拡大や、パートナーの育休取得を後押しする職場環境の改善といった制度設計も急がれます。
そして何より重要なのは、私たち一人ひとりの意識を変えることかもしれません。
「『母親なんだから頑張って当然』『昔はもっと大変だった』といった根性論は、医学的に全く根拠がありません。現代の核家族化といった社会環境の変化を無視して、個人の責任に帰結させるべきではないのです。
熊田さんが体験された『幽霊でもいいから誰かいてほしい』というほどの孤独感。これは、本来、集団で子育てをしてきた人間にとって、一人の女性が24時間体制で乳幼児の世話をするという、生物学的に見ても不自然な状況から生まれる、むしろ正常な反応ともいえます」(宋美玄先生)
「完璧な母親」という幻想からの解放
産後の女性は、「良い母親でいなければ」というプレッシャーを知らず知らず、自分に与えてしまっていて、そのことが、多くの女性を苦しめる一因にもなっています。しかし、完璧な母親など存在しません。子育ては試行錯誤の連続で、迷ったり悩んだりするのが当たり前です。
熊田さんのように、産後うつを経験しても、適切なサポートがあれば回復は可能です。そして、その経験は決して無駄にはなりません。同じ状況にある女性たちの支えになったり、社会をより良く変える力になったりするのです。
産後うつは、特別な病気として恐れるのではなく、誰にでも起こりうる自然な反応として理解し、社会全体でサポートする仕組みを作ること。医学的な治療と並行して、家族・地域・職場・行政が連携し、多層的な支援体制を構築していくことが求められています。
一人でも多くの女性が安心して子育てできる社会を実現するために、私たち一人ひとりができることから始めていきましょう。
※この記事は、産後うつの当事者である熊田梨恵さんへのインタビューと、産婦人科医・宋美玄先生の医学的見解を基に作成されました。症状や治療法には個人差があります。心配な症状がある場合は、必ず専門医にご相談ください。
【参考文献】
・“産婦人科診療ガイドライン―産科編2023” 公益社団法人 日本産科婦人科学会
・“周産期メンタルヘルスコンセンサスガイド2023” 日本周産期メンタルヘルス学会
・“エディンバラ産後うつ病質問票(EPDS)”
・“産前・産後サポート事業ガイドライン 産後ケア事業ガイドライン(令和6年10月)” こども家庭庁, (参照 2025-06-15)
〈取材協力者プロフィール〉
宋 美玄先生
〈取材協力者プロフィール〉
熊田梨恵(くまだ・りえ)
NPO法人パブリックプレス代表理事。2015年に第一子を出産後、産後うつを経験。これをきっかけに自身の抱えていた心の傷と向き合い、現在は大阪で女性向け自助グループ運営。トラウマケアのための一般向け講座も行う。ふだんは医療ライター。著書に『救児の人々』『胃ろうとシュークリーム』など。
山本尚恵
医療ライター。東京都出身。PR会社、マーケティングリサーチ会社、モバイルコンテンツ制作会社を経て、2009年8月より独立。各種Webメディアや雑誌、書籍にて記事を執筆するうち、医療分野に興味を持ち、医療と医療情報の発信リテラシーを学び、医療ライターに。得意分野はウイメンズヘルス全般と漢方薬。趣味は野球観戦。好きな山田は山田哲人、好きな燕はつば九郎なヤクルトスワローズファン。左投げ左打ち。阿波踊りが特技。