気になるキーワード「無痛分娩」#04
【無痛分娩体験談】ホントに安全? 痛くない? 費用が高くない? 無痛分娩経験者3人のリアルな声
「鼻からスイカを出すような痛み」と表現されることもある出産の痛み。近年、その痛みを麻酔によって和らげる「無痛分娩」を選ぶ人が増えています。2025年10月からは東京都で費用の補助も始まり、関心は高まる一方です。
しかしながら、無痛分娩を選びたいけれど、費用もかかる上、「麻酔がうまく効かなかった」という声が聞こえることもあり、迷っている人は少なくないでしょう。
そこで今回、無痛分娩を経験した3人の女性にインタビューしました。なぜ無痛分娩を選んだのか、実際のお産はどうだったのか、リアルな声をお届けします。
ケース1:「仕事復帰は早かったけれど、鉗子分娩の影響か、産後2年間、尿漏れが続いた」
フリーランスの編集者・ライターとして働くトミカワさん(仮名)は、東京都在住。約10年前、第一子の出産時に無痛分娩を経験しました。トミカワさんの母親も、無痛分娩を選択していたこともあり、「妊娠当初から無痛分娩以外の選択肢が考えられなかった」と言います。
「フリーランスには産休なんてありませんから、産後も『なるべく早く仕事を再開したい』と思っていました。無痛分娩は痛みを軽減できる分、産後の体力の回復も早いといわれています。そのため産院探しも、無痛分娩ができることを条件に探していました。追加費用が15万円ほどかかりましたが、それ以外の選択肢が頭になかったので、高いとは思いませんでした」
幸い、陣痛が来てから麻酔を入れるオンデマンド型の無痛分娩ができる総合病院が自宅近くにあり、分娩の予約も無事にできました。しかし、出産予定日の1ヶ月前に破水し、急きょ入院することに。ほどなく陣痛も来て、なし崩し的に出産が始まりました。
「担当の先生からは『一応、無痛分娩の準備はするけれど、麻酔がうまく効かないかもしれないよ』という説明がありました」
事前の懸念をよそに、硬膜外麻酔が投与されると、次第に痛みが和らいでいきました。立ち会い出産のため分娩室に一緒に入っていたパートナーと、当時気になっていた映画の話ができるほど余裕もできました。
しかし、痛みが和らいだ一方で陣痛が進まなくなるという事態に。そのため、陣痛促進剤を投与したものの、それでもなかなか「いきみきれない」状態が続き、最終的には鉗子(かんし)分娩での出産となりました。
鉗子分娩とは、トングのような見た目をした「鉗子」という器具で赤ちゃんの頭をはさみ、引き出す出産方法です。赤ちゃんの頭や顔に傷や圧迫のあとができることがありますが、通常は数日で目立たなくなります。また母体には、会陰の傷が大きくなることがあったり、まれに「神経因性膀胱(膀胱麻痺)」という、膀胱の感覚がなくなり排尿のコントロールができなくなる症状が生じたりすることがあります。
当時の状況をトミカワさんは、こう話します。
「いきめなかったので頑張って産んだという感覚もないし、赤ちゃんが引っ張り出された感覚もありませんでした。気が付いたら赤ちゃんが生まれていて、泣き声が聞こえてきたという感じでした。出産の達成感はあまり得られなかったかもしれません」
けれども、希望だった産後の体力温存は、出産後まもなくから、産院に持ち込んだPCで仕事を再開できるほどしっかりできていました。一方で、鉗子分娩の影響か、産後2年ほど尿漏れに悩まされたと明かします。
「ライブに行くのがすごく好きで、産後も夫に子どもの世話を任せて、一人で参加していました。その時に『あ、来たぞ。尿漏れしたぞ』みたいな感覚が2年ぐらい続いていました。でも、自分では『こういうものかな』と、特に気にしてはいませんでした。だって、産んだ後の人に『尿漏れってどれくらい続いてましたか?』とか聞かないじゃないですか。だから、長かったんだっていうのを後から知りました」
トミカワさんのお産はある意味、無痛分娩のメリットとデメリットを両方享受したお産だったかもしれません。
ケース2:「助産師として壮絶なお産の現場を見てきたからこそ選んだ」
タナカさん(仮名)は、第一子と第二子の出産時の2回、無痛分娩を経験されています。北海道で助産師として多くのお産に立ち会ってきたタナカさんは職業柄、無痛分娩を選びたいという思いが強かったと言います。
「妊婦さんが痛みに耐えている姿を見ているうち、『私には痛みに耐えられる自信がない。無理だ』と感じるようになりました。それで、自分が産むなら無痛分娩を選択したいと思っていました。痛みを緩和できる方法があるなら、それを選択しない理由はないかなと」
出産は、北海道の産院で。個人病院でしたが、陣痛が来てから麻酔を依頼するスタイルが可能だったため、それを選択。麻酔が効き始めると、痛みは劇的に変化しました。
「お腹の張りはありましたが、痛みはまったくというほど感じなくなりました。お産にかかった数時間のうち、痛みを感じたのはトータルで5分程度だったという感覚です」
タナカさんも、産後の回復がとても早かったと話します。
「産後はよく『フルマラソンを走ったくらい疲れる』といわれますが、私の場合は2回のお産とも、痛みをほぼ感じなかったため、疲れがほとんどなかったです。おかげで産後すぐから元気いっぱいに過ごせました」
なお、タナカさんの場合、無痛分娩にかかった追加費用は、地方の個人病院だったこともあり約7万円でした。「産後の状況を考えると安いと思います」と、その価値を実感していました。
ケース3:無痛分娩であっても、自分で選び、出産できたことが自信になった
熊本県在住のホンダさん(仮名)が、第一子を無痛分娩で出産されたのも、約10年前のことでした。周囲に医師や看護師などの医療従事者が多く、そうした友人から無痛分娩を勧められたことで興味を持ったそうですが、最大の決め手は出産費用だったと言います。
「私が出産した熊本の産院は、無痛分娩にしても通常のお産とかかる費用が変わらなかったんです。それで『費用が同じなら無痛にしたほうがいいかな』という理由から選択しました」
ホンダさんも陣痛が来てから麻酔を投与する、オンデマンド型の無痛分娩で出産をしました。無痛分娩を多数行っている産院ならではの手際の良さで、「お産全体を通して、麻酔の針を背中に入れられる時が一番痛かったかもしれない」と振り返るほど、麻酔の効果は高かったようです。
「重い生理痛のような痛みがあったのですが、麻酔が効き始めると和らぎました。あまりに効果があったので、ちょっとびっくりしたくらいです」
途中で陣痛が弱まり、麻酔を一時中断する場面もありましたが、最終的には約7時間という、初産にしては驚異的な短時間で無事出産にいたりました。産後の回復も早かったものの、乳腺炎などのマイナートラブルには苦労したそうです。
そんなホンダさんは、無痛分娩を「自分で選択したこと」が、出産に対する不安の払拭につながったと話します。
「初めてのお産だったので、いろいろ情報を集めていても不安がつきまとっていました。でも、『無痛分娩で産む』という選択をしたことから、出産に対して前向きな気持ちを持てるようになったんです。不安よりも自分の選択に対する自信が勝ったという感じでしょうか。その自信がお産の時に勇気となっただけでなく、今の自分の子育ても助けてくれているような気がしています」
3人の経験から見える、無痛分娩のリアル
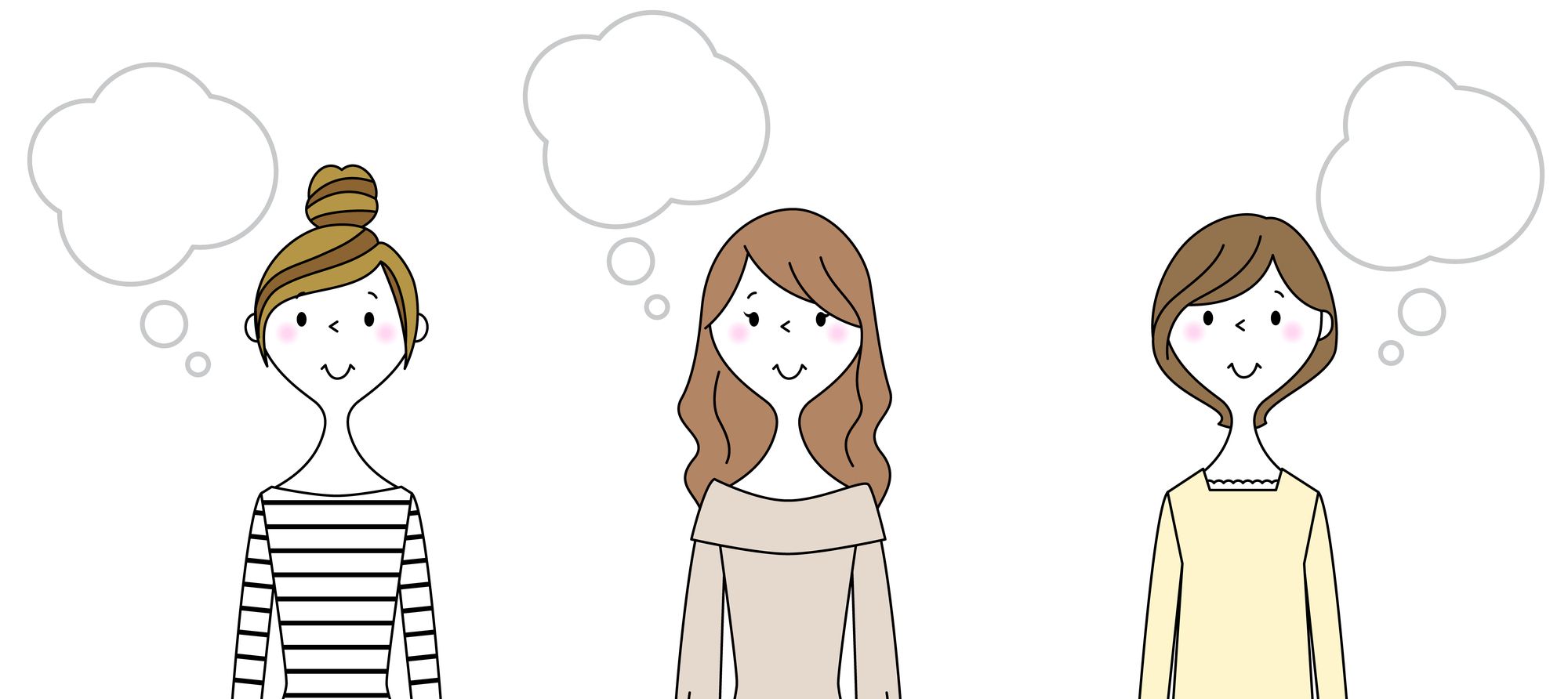
今回お話を伺った3名の、無痛分娩の経験をあらためてまとめると、その実態が三者三様であることがわかります。
・痛み
タナカさんは「まったく痛くなかった」、ホンダさんは「重い生理痛程度」、トミカワさんは「映画の話ができる余裕」があったと、痛みの感じ方には個人差がありました。
・費用
熊本県在住のホンダさんは「追加費用なし」、北海道在住のタナカさんは「約7万円」、東京在住のトミカワさんは「約15万円」と、病院や地域によって大きな差があることがわかります。
・経過と産後
タナカさんが「まったく疲れがなかった」と理想的な経過だったのに対し、トミカワさんは促進剤・鉗子分娩を経て産後の尿漏れを経験。ホンダさんもお産とは別に、産後に乳腺炎などのトラブルがありました。無痛分娩で出産そのものの痛みを和らげても、産後によくあるトラブルまでがなくなるわけではないようです。
なお、「次のお産でも無痛分娩を選ぶか」という質問に対しては、全員が「選ぶ」と答えていました。
痛みを経験しなくても母親になれる。大切なのは「自分で選んだ」という納得感
今回お話を伺った3名の経験は、無痛分娩が一様ではないことを浮き彫りにしました。麻酔の効果や産後の経過は人それぞれであり、理想的なお産になることもあれば、思わぬトラブルに見舞われる可能性もゼロではありません。
しかし、共通していたのは、それぞれがご自身の状況や価値観に基づいて「無痛分娩」という選択肢を主体的に選び取っていたことでした。
タナカさんの言葉が印象的です。
「お産神話ではないですが、痛みを経験せずとも母親にはなれます。お産の方法で母親になれるかどうかが決まるなんてことはありません。いろんなお産の方法がある中で、自分が選んだ方法に自信を持てるのがよいと思います」
無痛分娩はあくまで選択肢の一つ。大切なのは、さまざまな情報を得た上で、自分自身が納得できるお産の形を見つけることなのかもしれません。
山本尚恵
医療ライター。東京都出身。PR会社、マーケティングリサーチ会社、モバイルコンテンツ制作会社を経て、2009年8月より独立。各種Webメディアや雑誌、書籍にて記事を執筆するうち、医療分野に興味を持ち、医療と医療情報の発信リテラシーを学び、医療ライターに。得意分野はウイメンズヘルス全般と漢方薬。趣味は野球観戦。好きな山田は山田哲人、好きな燕はつば九郎なヤクルトスワローズファン。左投げ左打ち。阿波踊りが特技。















