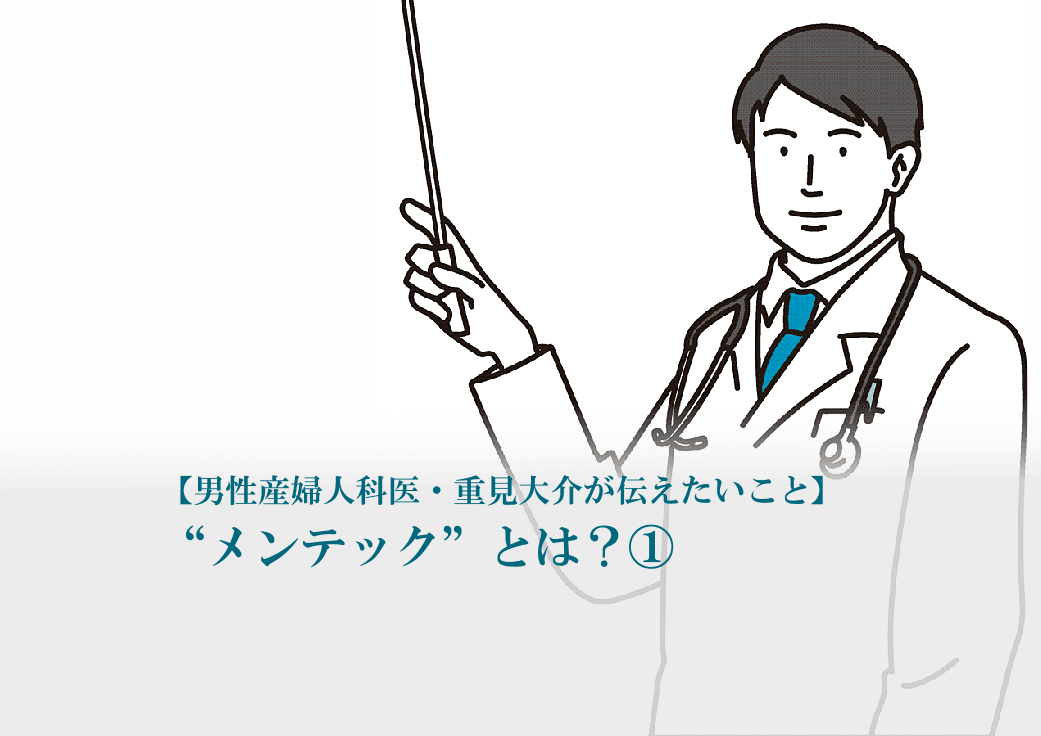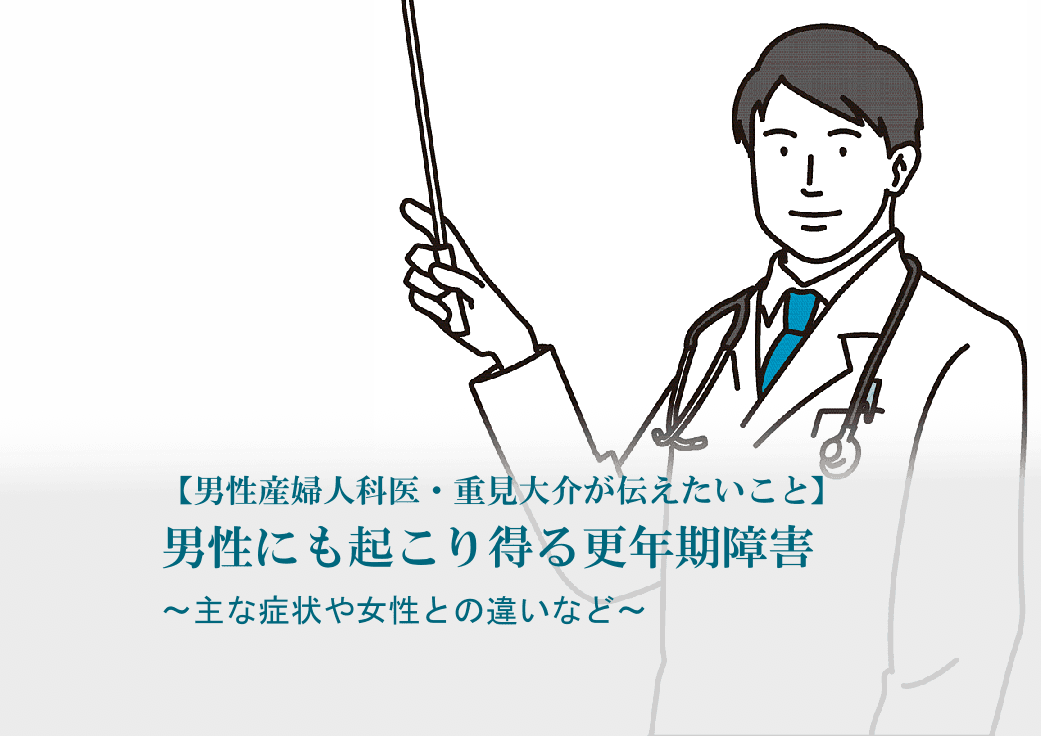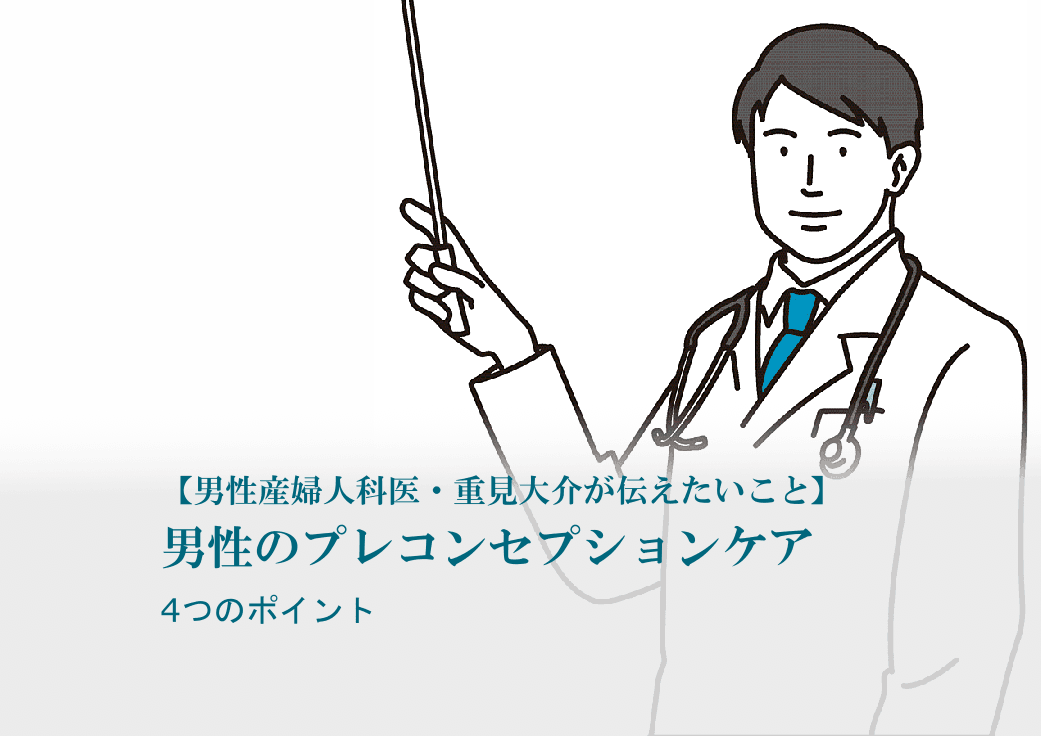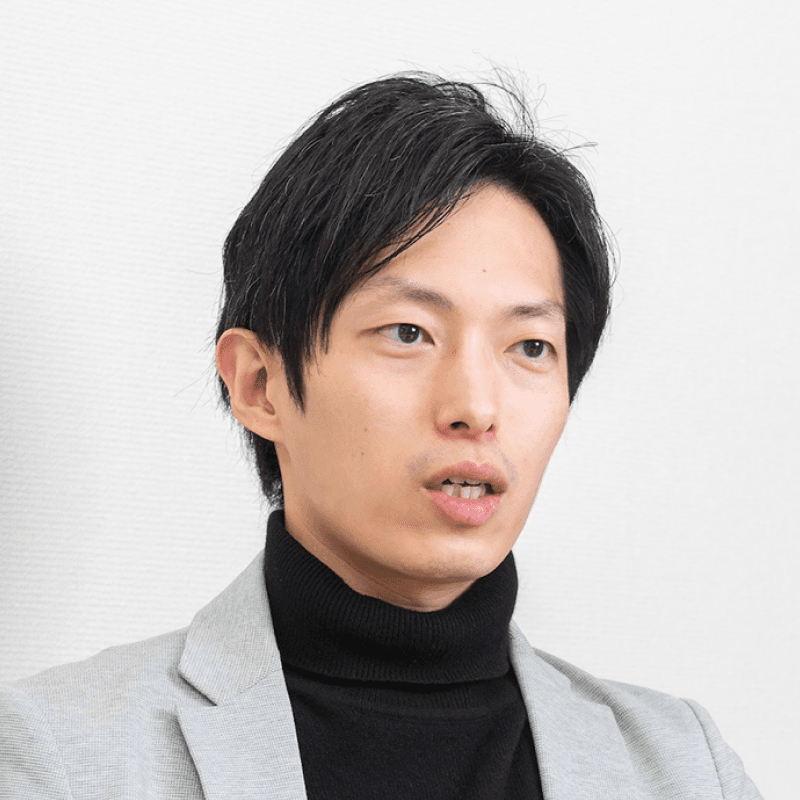男性産婦人科医・重見大介が伝えたいこと #07
“メンテック”とは?:男性の健康を支える最新テクノロジーとサービス②
前回に引き続き、男性のQOL向上を後押しする「メンテック」について取り上げます。
「メンテック」って何?
「メンテック」の定義については前編の記事でも解説しましたが、改めて振り返っておきましょう。
「フェムテック」(女性×テクノロジー)という言葉に対し、最近では「メンテック」(男性×テクノロジー)という分野も登場していることをご存知でしょうか。これは、男性特有の悩みをテクノロジーで支援・解決する分野で、「Male(男性)」と「Technology(テクノロジー)」を組み合わせた造語になっています。
メンテックが登場した背景には、男性特有の健康課題を語る・共有する上での難しさやハードルがあるとされています。というのも、男性は「ジェンダーバイアス」によって、自身の健康問題(特に性や生殖に関するもの)を周囲に打ち明けづらく、適切なケアを受けられないケースも少なくありません。また、男性の健康に特化して健康情報を提供される機会もかなり少ないと言えるでしょう。メンテックは、このような課題をテクノロジーの力で改善・解決していくことを目指すものになります。
男性の健康は女性の健康にも深く関わりますし、プレコンセプションケアや妊活ではまさに「共有する課題」になります。
後編の本記事では、「メンタルヘルス」「前立腺・泌尿器疾患」「パフォーマンス&フィットネス」へのプロダクトやサービス事例を紹介していきます。
「性機能」「毛髪・肌・外見」に関するサービス
前編の記事では、ED(勃起不全)や男性不妊に対するオンライン診療と在宅検査、AGA(男性型脱毛症)やスキンケアのサブスク型サービスなどを紹介しました。主に海外で増加していますが、日本でも散見されます。
共通点は、問診→検査・治療→フォローアップまでの一連の体験をスマホで完結させ、価格や支払い方法を明確にし、継続支援(リフィル・定期配送・記録アプリ)で「続けやすさ」を高めている点でしょう。こうした工夫はこれまでの「受診しにくさ」「通院の難しさ」を克服でき得るメリットがあるので、期待したいところですよね。

男性メンタルヘルスへのメンテック事例
男性は不安・抑うつを抱えても受診や相談をためらいがちです。メンテック領域では、その“最初の一歩”を後押しするようなサービスが増えています。
匿名・非対面の相談導線
テキストや音声メッセージ中心の非同期型カウンセリング、夜間や週末の短時間ビデオセッションなど、働き方に合わせた選択肢が広がっています。
アプリでのセルフケア
認知行動療法(CBT)に基づく短いワーク、睡眠・活動・気分のトラッキング、ストレス時の呼吸法ガイド、マインドフルネスのガイド音声などが活用されています。
男性に向けたUXの工夫
弱さを認めにくい文化的背景へ配慮したコピーやデザイン、「パフォーマンスを上げるメンタル整備」としてのリフレーミングなどが、UX(製品やサービスをユーザーが利用する際の体験)に採用されていることが多い印象です。
スクリーニングの標準化
国際的に性能が評価された質問票(スクリーニング用ツール)を定期配信し、変化を見える化しているサービスも多くあります。必要時は専門医へスムーズに繋げます。
例えば、国内外で以下のようなサービス・プロダクトがあります。
HeadsUpGuys(カナダ)
男性のうつ病・自殺予防に特化。自己評価、セルフヘルプ記事、回復ストーリー、医療者検索、家族・同僚向け支援ガイドを提供。学術誌でも紹介されています。
Men’s Shed(豪州)
作業小屋(Shed)でのものづくり・交流を通じて孤立を防ぐコミュニティネットワーク。地域での居場所づくりに強みがあり、オンラインだけでは得られない効果を期待できそうですね。
cotree(日本)
男性に特化したものではありませんが、公認心理師・臨床心理士が多数登録しており、テキスト/音声通話/ビデオ通話によるオンラインカウンセリングと、簡易マッチング診断が可能。
なお、強い希死念慮・急性の自傷リスクがある場合は、アプリやチャットのみでは十分な対応が難しいです。自覚症状が軽いうちに使い始めるとしても、救急受診や地域の相談窓口につながる案内が準備されているか、事前に確認しておきましょう。
前立腺・泌尿器疾患に関するメンテック事例
加齢とともに頻度が上がる排尿関連症状(頻尿、夜間頻尿、尿が出にくい、尿の勢いが弱い、残尿感など)は、放置すると生活の質を大きく下げてしまいます。メンテックによって、早期発見と継続的なフォローにつながるかもしれません。
在宅スクリーニング
自己採取のPSA(前立腺特異抗原:前立腺癌、前立腺肥大症、前立腺炎などで高値になる)検査キットや、尿検査の宅配・解析サービスが海外では増えています。アプリで結果を確認し、泌尿器科の遠隔相談につなげられます。
症状の見える化アプリ
夜間頻尿・尿勢低下・残尿感などを記録し、国際前立腺症状スコアを自動集計できるサービスなどがあります。自分自身でも症状への意識が高まりますし、治療前後の比較が容易になるメリットもあります。
排尿機能の自宅測定
スマホや小型デバイスでの尿流量測定ができ、水分摂取と排尿間隔の最適化についてアドバイスをもらえるアプリなどが登場しています。
治療と生活習慣の両輪を支援
薬物治療の継続率や適切な服薬率アップ、骨盤底筋トレーニングやカフェイン制限のリマインド機能を組み合わせ、再診時に医師と情報共有できるものも出てきています。
例えば、国内外で以下のようなサービス・プロダクトがあります。
imaware(米国)
自宅で採血→認定ラボで解析し、PSAを検査できます。米国Mayo Clinicの泌尿器科との連携も可能なサービスです。
iUFlow(排尿記録アプリ)
水分摂取量や排尿量を自動集計し、医師と共有できます。日本語ストアページもあり。
なお、前立腺癌や前立腺肥大症の診断・治療は専門医による対面評価が必要です。あくまで、在宅検査は“ふるい分け”と捉え、異常値や症状悪化時は必ず受診をしてくださいね。在宅検査の正確性を信頼できそうかも事前にチェックしておきましょう。
パフォーマンス&フィットネスを支えるメンテック事例
体力・睡眠・回復の質は、仕事や家庭でのパフォーマンスに直結します。この分野では「ウェアラブル×AIコーチ」が中心となっています。

回復指標の活用
心拍数、心拍変動、睡眠状況、皮膚温などを統合し、“今日は追い込む/休む”の判断を日々提案してくれるサービスがあります。無理を減らし、ケガのリスクを抑えます。
AIフォーム解析
スマホカメラでスクワットやデッドリフトなど筋トレのフォームを撮影し、関節角度や荷重の偏りを自動解析してくれます。自宅トレーニングでも安全性と効率を両立することに役立ちそうです。
栄養・体重管理
食事の写真を送ると概算栄養素を推定し、たんぱく質や食物繊維の不足をリマインドしてくれるプロダクトも登場しています。中年期のサルコペニア(加齢によって筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下した状態)予防にも有用かもしれません。
総合プログラム
睡眠・筋トレ・有酸素運動・ストレッチの週次プランを提示し、達成度をスコア化することで、達成感を得られ、継続を後押しするようなサービスも増えてきています。
例えば、国内外で以下のようなサービス・プロダクトがあります。なお、以下はメンズに限ったサービスではありません。
Oura Ring(指輪型デバイス)
指輪型デバイスを付けておくことで、体温・心拍・睡眠を計測し、朝のコンディション(回復具合)と睡眠スコアを表示します。就寝習慣の改善に有効かもしれませんね。
Future(1対1オンライン・パーソナルトレーニング)
専属コーチが週次プランを作成。Apple Watch等のデータ連携で強度管理とフィードバックをしてくれます。こちらはAIではなく実際のトレーナーが対応するサービスのようです。
Fitbod(筋トレ最適化アルゴリズム)
直近の使用筋群・回復度・設備などから次のワークアウトを自動的に提案します。こうしたものは、人とやり取りするのが苦手な男性でも使いやすいかもしれませんね。
サービス利用における注意点
1. 医療(対面受診)の完全な代替ではない
アプリや在宅検査は受診ハードルを下げるツールとして便利です。しかし、血尿、急な体重減少、強い痛み、急激な気分変調などの“赤信号”があれば速やかに対面受診をしてくださいね。
2. エビデンスの確認
研究結果やガイドラインなどの裏付けがあるか、アルゴリズムの妥当性をどう検証しているかをチェックしましょう。口コミやインフルエンサーの体験談だけで判断しないことが大切です。
3. プライバシーとデータの扱い
性・メンタルヘルス・前立腺疾患といったセンシティブなデータを扱います。暗号化、第三者提供の条件、退会時のデータ削除手続き、2段階認証の有無などを事前に確認しておきましょう。
4. 課金モデルと継続可能性
こうしたサービスやアプリの多くはサブスク型です。最低利用期間・解約金の有無などを事前に把握し、自身の生活リズムに合うかを見極めましょう。
5. 多様性への配慮
「男らしさ」を狭く定義する表現を過度に用いていたり、身体的特徴に強い価値を置いたりするような設計のサービスは、ストレスの元になりやすいです。自尊感情を傷つけない言葉選びをしているかも、良いサービスの指標と言えるかもしれません。
男性の健康は女性の健康にも深く関わるもの
男性の健康は、女性の健康にも深くつながっています。
睡眠不足や抑うつは家庭の雰囲気や育児の分担に影響し、パートナーのストレスや不眠を招くことがあります。前立腺・泌尿器の症状や性機能の悩みは、カップルの関係性や妊活の計画に影響するでしょう。さらに、生活習慣病や過度な飲酒は将来の介護負担や家計にも響いてしまいます。
だからこそ「自分ごと」を「ふたり(家族)ごと」として考えることが大切です。定期受診、運動習慣、睡眠改善、飲酒・喫煙の見直し、メンタルヘルスのセルフチェックなど、「自分の健康は今の(将来の)パートナーにも影響するんだ」という意識をぜひ持っていただけたらと思います。もちろん、パートナーがいなくても、自分自身の健康に向き合うことの大切さは変わりません。
メンテックは日本でもますます発展・普及していくと思います。本記事も参考にしていただき、体調管理や健康向上に役立てていただければ幸いです。