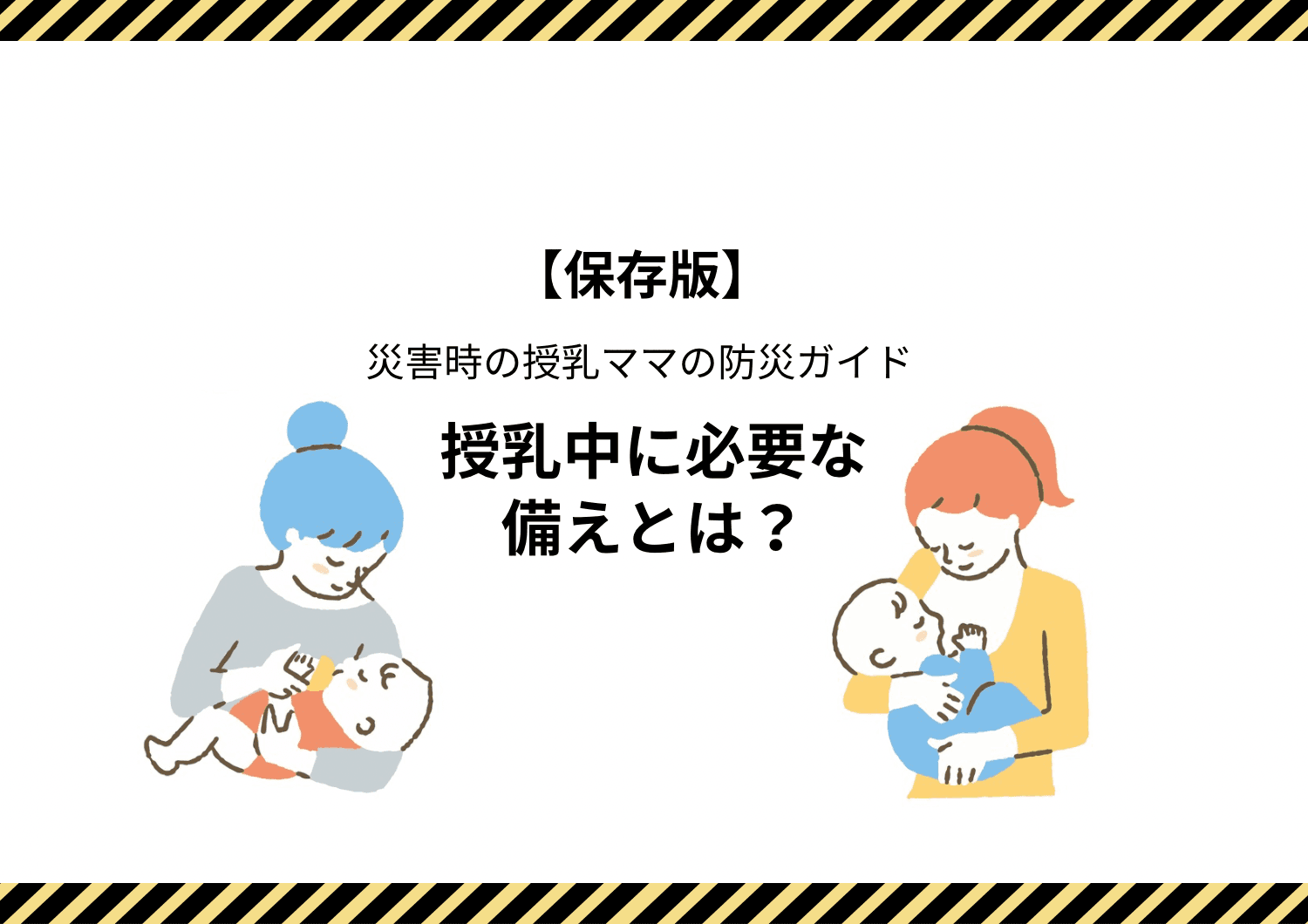男子校からの性教育依頼が増加、一方で解消されない産婦人科への抵抗感…日本のSRHRの現在地【重見大介先生インタビュー】
本サイトでは、SRHR(Sexual and Reproductive Health and Rights:性と生殖に関する健康と権利)の理念に基づいた記事を発信していますが、日本ではこの考え方がまだ十分に浸透していません。特に“Rights”すなわち「権利」の部分が、教育現場や診療現場など多くの場面で、悲しいかな重視されているとはいえない現状があります。
こうした問題について、現場での実体験に加え、SNSで積極的に発信していることから一般の人々の視点にも理解の深い、重見大介先生にお話をうかがいました。
SRHRという語を知ったのは、比較的最近
産婦人科医なら誰もが、SRHRの理念が身についていて、それに基づいた診療などをしているかというと、実はそうでもありません。現在の医学部の最新のカリキュラムや教科書の内容までは把握していませんが、少なくとも自分の学生時代には授業で扱われていませんでした。きっといまでも、徹底されているわけではないように思います。
私がSRHRという語を知ったのは、比較的最近のことです。
かつて勤務していたのが大学病院ということもあって、重症な患者さんを担当することが多く、そうなると医師同士でディスカッションするのは、目の前の患者さんをどう治療するかということに終始します。つまり、Healthにフォーカスする日々を送っていました。
「社会的な視点」をもつ
転機は、研究スキルの習得を目的に公衆衛生大学院に進んだことです。キャリア7〜8年目、産婦人科専門医の資格を取得したあとのことです。30人ほどのクラスで、産婦人科医は私ひとり。そこでクラスメイトから、
「日本の出生数は年間100万人を下回る水準に落ち込んでいる一方で、人工妊娠中絶件数は年間10万件をくだらない。少子化が深刻化するなか、望まない妊娠や中絶がこれほど多い現状について、産婦人科医や専門組織はどう考え、どんなアクションをしているの?」
という質問をされたのです。公衆衛生とは、ある集団が抱える健康課題の要因を、個人ではなく社会や環境に求め、それをどう解消すればその集団に健康がもたらされるかを考える学問のこと。「社会的な視点」に立つと、こうした問いが出てくるのです。
私はそのとき、すぐに答えられませんでした。なぜなら、Healthに集中していた大学病院では、考えたことがなかったからです。ほかにも緊急避妊薬へのアクセスのむずかしさ、HPVワクチンの接種率の低さ、さらには海外では普及しているのに日本では使えない治療薬……まさにRightsにまつわる課題が自分の専門領域にたくさんあることにはじめて気づき、向き合おうと心に決めたのが、公衆衛生大学院でした。
「性教育を受ける」というRights
いま私は、SNSでの情報発信や性教育活動に力を入れていますが、そのなかでもSRHRの課題を感じています。学校での講演や企業研修は、年々依頼が増えていて、関心の高まりを感じます。特に最近は、男子校からの性教育に関する依頼が多いです。
中学1、2年生ぐらいだと、話の内容によってはちょっとザワついたり笑い合ったりすることはありますが、だいたいは真面目に聞いてくれます。大人はすぐに「いやらしいこと」と結びつけがちですが、子どもたちの反応は「性感染症、まじで気をつけないと!」など素直なものです。脅かす意図からではなく、「過去に患者さんでこういう人がいてね」というリアルなエピソードとともに「社会的な視点」も併せて伝えられるのが、私が性教育をする意味だと思っています。

気になるのは、10代で包括的性教育を受けられたとして、大人になるまで同じ機会はもうないのだろうということです。私自身も、包括的な内容ではありませんでしたが中高生のころ性教育の授業はあったはずなのに、ほとんど覚えていません。
この先パートナーができる、子どもをもつ機会があるとしても、それまでに学びを重ねる機会がなく、そうなるとどうしてもネットにある情報、友だち同士で共有される情報が多くを占めるようになります。調べ方にもよりますが、不確かなものも少なくなく、誤解や偏見も多く含まれています。
医師と患者のコミュニケーション
身体について気になることがある女性には、ぜひ気軽に産婦人科に来ていただきたいです。とはいえ、XなどのSNSを見ると、産婦人科受診に抵抗のある女性が少なくない様子が見て取れます。
私も自分が産婦人科医として働くようになってから、医師とひと口にいってもいろんな人がいるなぁと感じるようになりました。お産のスペシャリストがいれば、子宮や卵巣のがんを手術するのが得意な医師もいて、専門領域が違うと、価値観も働き方も、患者さんへの接し方も違ってきます。外来で患者さんと話すことがほぼなく、手術ばかりしているタイプの医師なら、コミュニケーションに気を配るより、治療率を挙げるため自分の腕を磨くことに注力するのは、ある意味で合理的でしょう。
それでも、すり合わせが必要な場面は当然あります。たとえば、がん治療のために子宮を摘出したほうがいいけれど、患者さんは子どもを自分で産む将来を望んでいるというケース。「医師としてはこう判断したけど、あなたはどうですか?」と伝え、話し合いによって何を優先するかを決めていく必要があります。HealthとRightsの両方にかかわるコミュニケーションです。
産婦人科への抵抗感はどこから?
一方、外来で接する患者さんのなかには、ご自身の過去の経験が影響して受診に抵抗があるのかなと感じる方もいます。「医師からの冷たい言葉や心ない態度で傷ついたことがあって、ずっと受診できませんでした」という方、診察時に雑に扱われたと感じた経験がある方、男性パートナーから酷いことをいわれてトラウマになり、「自分の身体に自信がなくて、たとえ病院でも人に見られるのがイヤでした」という方……背景はさまざまです。

こうしたことは患者さん側から積極的に話してくれるものではなく、医師は「なぜこんなに抵抗が強いんだろう」と考えながらの診療になります。医師側の要素と、患者さん側の要素、その両方が複雑に絡み合っているというのが、現場での実感です。
産婦人科はもともとセンシティブな領域を扱うところなので、対人コミュニケーションが重要な要素であることは間違いありません。総合的に患者さんの体験がどうなるのがいちばんいいのかという視点をもつことが、医師側に求められる時代であるといってもいいでしょう。受診しやすい、相談しやすい医師が“見える化”されて、患者さん側は受診する先を選べるようになるというのが、理想です。
「よい医療体験」を重ねていくために
現状でそれがむずかしいと感じる理由のひとつに、産婦人科にかぎった話ではないのですが、医師個人へのフィードバックの仕組みがほぼ整っていないことがあると思っています。患者さんが不満を持つと、だいたいはその病院やその医師の外来にはもう来なくなるので、声が医師には届かないままです。
私はオンライン相談事業を運営しているのですが、そこではすべての利用者の方にアンケートを送り、返ってきた回答をすべて医師個人にフィードバックしています。ポジティブな声はもちろん、「おっしゃっていることはわかるのですが、言葉尻が強くて傷つきました」といったネガティブな声もあり、どちらも等しく伝えます。統計的な定量評価も、定期的に実施しています。
もちろん、同じコミュニケーションでも利用者の方によって正反対の受け取り方をすることはありえます。でも、フィードバックがほぼない環境がつづくと、双方とも現状に甘んじなければならない。医師側がコミュニケーション面のフィードバックを受けてアップデートしていく仕組みをつくりたいと思っていて、現在のオンライン相談事業ではある程度実現できているように感じます。
今後は、オンラインで相談だけでなくさまざまな診療もできるよう、社会はどんどん変わっていくでしょう。そうすると、自分がどこにいても同じ医師に診てもらいやすくなります。多くの医師にとっても、患者さんのライフステージが変わっても継続して受診してくれるのは、うれしいことです。みなさんが複数の「主治医」を持っている、そんな時代もそう遠くないかもしれません。
医師と患者さん双方にとって「よい医療体験」を重ねていけるのが、目指すべき理想だと思います。
(構成:三浦ゆえ)
重見大介
産婦人科専門医、公衆衛生学修士、医学博士。産婦人科領域の臨床疫学研究に取り組みながら、遠隔健康医療相談「産婦人科オンライン」代表を務め、オンラインで女性が専門家へ気軽に相談できる仕組み作りに従事している。他に、HPV(ヒトパピローマウイルス)と子宮頸がんに関する啓発活動や、各種メディア(SNS、ニュースレター、Yahoo!ニュースエキスパート)などで積極的な医療情報の発信をしている。
三浦 ゆえ
編集者&ライター。出版社勤務を経て、独立。女性の性と生をテーマに取材、執筆を行うほか、『女医が教える本当に気持ちのいいセックス』(宋美玄著、ブックマン社)シリーズをはじめ、『小児科医「ふらいと先生」が教える みんなで守る小児性被害』(今西洋介著、集英社インターナショナル)、『性暴力の加害者となった君よ、すぐに許されると思うことなかれ』(斉藤章佳・にのみやさをり著、ブックマン社)、『50歳からの性教育』(村瀬幸浩ら著、河出書房新社)などの編集協力を担当する。著書に『となりのセックス』(主婦の友社)、『セックスペディアー平成女子性欲事典ー』(文藝春秋)がある。
【あわせて読みたい】
男性に知っておいてほしい、女性の健康を守るために大事な5つのこと【男性産婦人科医が提言】→配信後リンク貼る