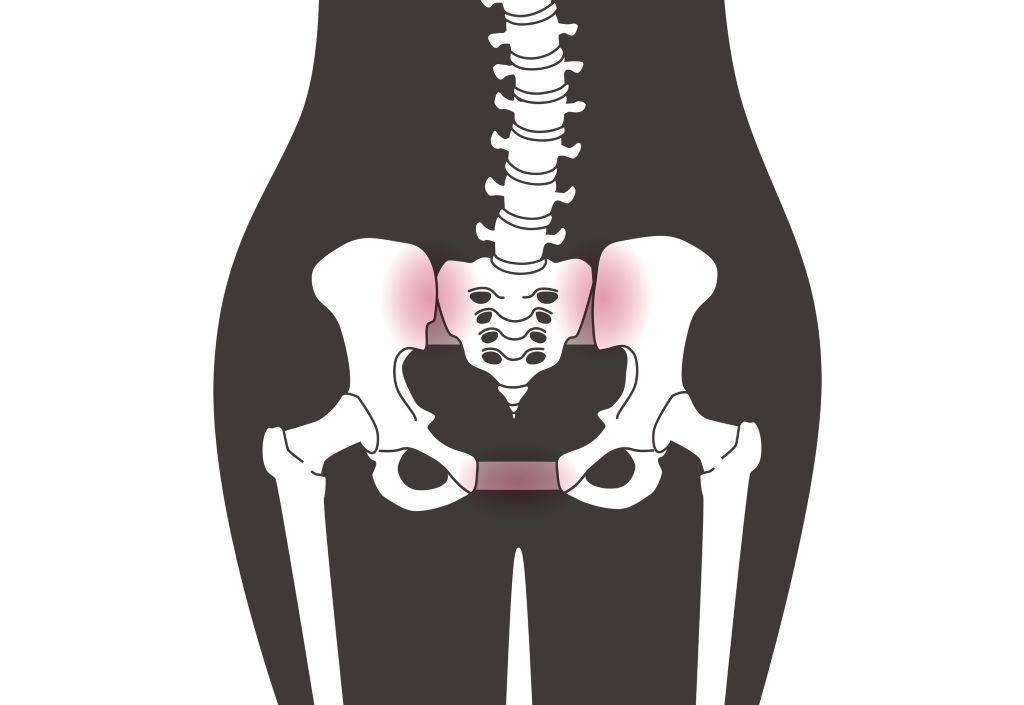産婦人科医やっきーのトンデモ医療観察記③
胎内記憶ってあるの?
こんにちは、産婦人科医やっきーです。
前回、「大事なのは『楽しく読めること』 産婦人科医やっきー先生がやって来た! デマに負けない正しい知識の伝え方とは?」にてインタビュー記事を掲載いただきました。
宋先生との対談は実に刺激的であり、産婦人科医療発信者として勉強になることが非常に多かったですね。
しかし、あの記事には大事なことが抜けています。
対談が終わったとき、「書籍の紹介もしとくね!」というご提案をいただきました。本を出したばかりの者にとってはこの上なくありがたいお話です。
「ありがとうございます、嬉しいです!」と返答した私に対し、宋先生は満面の笑みで「あとトンデモ医療観察記の第三弾もよろしく!」と言い残して去っていきました。
本の宣伝というエサに釣られてやってきた哀れなシロクマに、すかさず記事の要求をする。さすが宋先生、熟練の一本釣り漁師のごとき無駄のない動きです。
私は船上でビチビチと跳ね回りながらただただ感服するしかありませんでした。私もああならなければならないと思いつつ、自室で泣きながらこの原稿をしたためています。
さて今回、宋先生からリクエストされたテーマは「胎内記憶ってあるの?」です。
胎内記憶、つまり「お母さんのお腹の中での出来事を憶えている」とされる現象のことですね。
胎内記憶ってどんなもの?
……このテーマを提示された時、率直に「マジか」と思いました。さては私のことを使い捨てのシロクマだと思っておるな? 実際その通りだけど。
なぜこんなに私が狼狽えているかと言いますと、胎内記憶というのはトンデモ医療……というよりスピリチュアルがだいぶ入った概念であることに加え、よくない方向のビジネスに容易に繋がりうるためです。これについて言及するにはちょっと気合いが要るのです。
詳しく説明しましょう。
「人々の記憶は宇宙で一つに繋がっている」というのは常識だと思いますが、それは赤ちゃんだけでなく、胎児も然りです。すなわち、人類の正の感情はすべて宇宙に散らばっているとも言い換えられます。
このたび私は引き寄せの法則を応用し、宇宙に散在する正の感情だけを抽出した水素水の製造に成功しました。これを1日1本飲むことによってハッピーな赤ちゃんが生まれるのです。今なら1本20万円のところ、特別に2000円で販売します。いかがでしょうか。
ごめんなさい調子に乗りました。
まじめな解説をしますと、赤ちゃんが胎児期の出来事を憶えているということはほぼありえません。
精神分析学の創始者として知られるフロイトは、1905年に「幼児期健忘」という概念を提唱しました。端的に言えば「赤ちゃんだった頃のことは誰も覚えていない」というもので、これは現在もなお明らかな矛盾が指摘されておらず、受け継がれています。
日本心理学会も「重要な出来事であっても、人はおおむね3歳以降のものでなければ思い出すことはできない」としており、ましてや胎児期の記憶があるという説は少なくとも医学会で一般的に受け入れられてはいません。
これは脳神経学的にも裏付けられており、記憶能力を司る脳の部位「海馬」が発達するのは、ヒトにおいて3歳頃であることが示されています。これより早期である胎児期や新生児期の記憶がその後も残っているということは、脳神経学的にも妥当とは言えません。
というわけで胎内記憶というのは、100年以上も前から医学会で支持され続け、その後も実証が次々になされている「幼児期健忘」に真っ向から対立する説であると言えます。
胎内記憶は本当に存在するのか?
そんな胎内記憶を積極的に唱えているのは誰かと言いますと、日本の産婦人科医・池川明です。彼は1999年から独自に、自身の患者や知人の協力を得て「胎内記憶」の聞き取り調査を開始し、小さな子どもたちに「お母さんのお腹の中にいた時のことを覚えてる?」などの質問を投げかけるアンケート調査を実施しました。
その結果、3500名以上の子どもを対象とした調査で、約3割の子どもが何らかの胎内記憶を持っていると回答した…というのが池川明氏の主張です。
しかしこれは、医学的に妥当な調査方法とは言えません。
そもそも前述の通り、小児というのは記憶能力が必ずしも確かとは言えないため、小児医学における問診の手法は他科のそれよりもかなりのテクニックを要します。
たとえば、2003年にこんな研究が発表されました。2~5歳児は「イエス」か「ノー」かで答えられる質問には「イエス」で答えやすい傾向があり、特に質問が難しくなればなるほど「イエス」が増える、というものです。このため、「お母さんのお腹の中は狭かった?」と聞けば「狭かった」と答え、「狭くなかった?」と聞けば「狭くなかった」と答える傾向があります。
他にも小児医学における問診・医療面接に関する研究はいくつかありますが、総じて「小児の問診では、その気になれば回答を誘導できてしまう」ということが判明しているため、オープンクエスチョン(イエスorノーでは答えられない質問)を使うべき、というのが現在のコンセンサスとなっています。
以上のことから、胎内記憶が存在することを裏付けるエビデンスは無く、また「胎内記憶は存在する」という研究の手法にも大いに疑問符が付くわけです。
とはいえ、ここまでで済めばまだマシです。
親が子どもと話している時に「お腹の中にいた時のことを覚えてる?」と言いながらキャッキャウフフとコミュニケーションの手段にするのは決して悪いことではありませんからね。

親子のキャッキャウフフで済めばいいけれど……
問題なのは、その胎内記憶の存在が良くない方向に利用されてしまう場合です。
たとえば、胎内記憶研究については「お母さんを選んで生まれてきたんだよ」と子どもが言った、というエピソードがしばしば紹介されます。これ自体はほっこりする話ではあります…が、これが一般化してしまうと非常に問題で、虐待やDVの被害当事者の自己責任化・二次被害につながる可能性もあります。あくまでも「ほっこりエピソード」にとどめて一般化は避ける、という各個人のリテラシーが必要になってきます。
加えて、前述の池川明氏が代表理事を務める「日本胎内記憶教育協会」という一般社団法人があるのですが、この基礎講座の受講料は66,000円となっております。
この基礎講座のページの見出しには「”魂の教育”のはじまり。」とデカデカと記載されており、その有無を言わせぬ説得力に私は「”魂の教育”がはじまるのか!!こいつぁ楽しみだぜ!!!」と膝を打たずにはいられませんでした。
さらに、そんな基礎講座を経ることによって「講師養成講座」を受講することもできるのですが、過去に講師養成講座は188,000円で販売された形跡もあります。
ええ商売してはりますなあ……と、私の中にないはずの京都人の血が思わず騒ぐ事態となってしまったわけですが、ともかく医学的な裏付けがきわめて希薄なはずの「胎内記憶」の講座が66,000円や188,000円というお値段で受講できるのです。
私が冒頭でご紹介した架空の水素水よりはお値打ちなので、気になる方は是非受講してみてくださいね。
私はやりません。

【参考資料】
心理学ってなんだろう「子どものときのことを覚えていないのはなぜ?」(日本心理学会)
Cristina M Alberini, Alessio Travaglia. “Infantile Amnesia: A Critical Period of Learning to Learn and Remember” J Neurosci. 2017 Jun 14;37(24):5783–5795.
「赤ちゃんは母親を選んで生まれてくる ——『胎内記憶』が私たちに示すもの」(致知出版社)
V Heather Fritzley, Kang Lee. “Do young children always say yes to yes-no questions? A metadevelopmental study of the affirmation bias” Child Dev. 2003 Sep-Oct;74(5):1297-313.)
胎内記憶教育 基礎講座(日本胎内記憶教育協会)
一般社団法人 日本胎内記憶教育協会について