【crumii医療ニュース解説】
体外受精の着床前検査(PGT-A)が35歳以上の方も対象に|2025年9月の新ルール解説
2025年9月5日、日本産科婦人科学会が体外受精における着床前検査(PGT-A)のルールを改定し、これまでより多くの方が検査を受けられるようになりました。特に注目すべきポイントは、35歳以上の女性であれば、過去の流産や移植不成功の経験がなくても検査対象となったことです。
この改定、不妊治療を受けている方にとって、選択肢が広がる重要な変更となりますので、詳しく解説していきます。
こちらの発表に基づくものです。
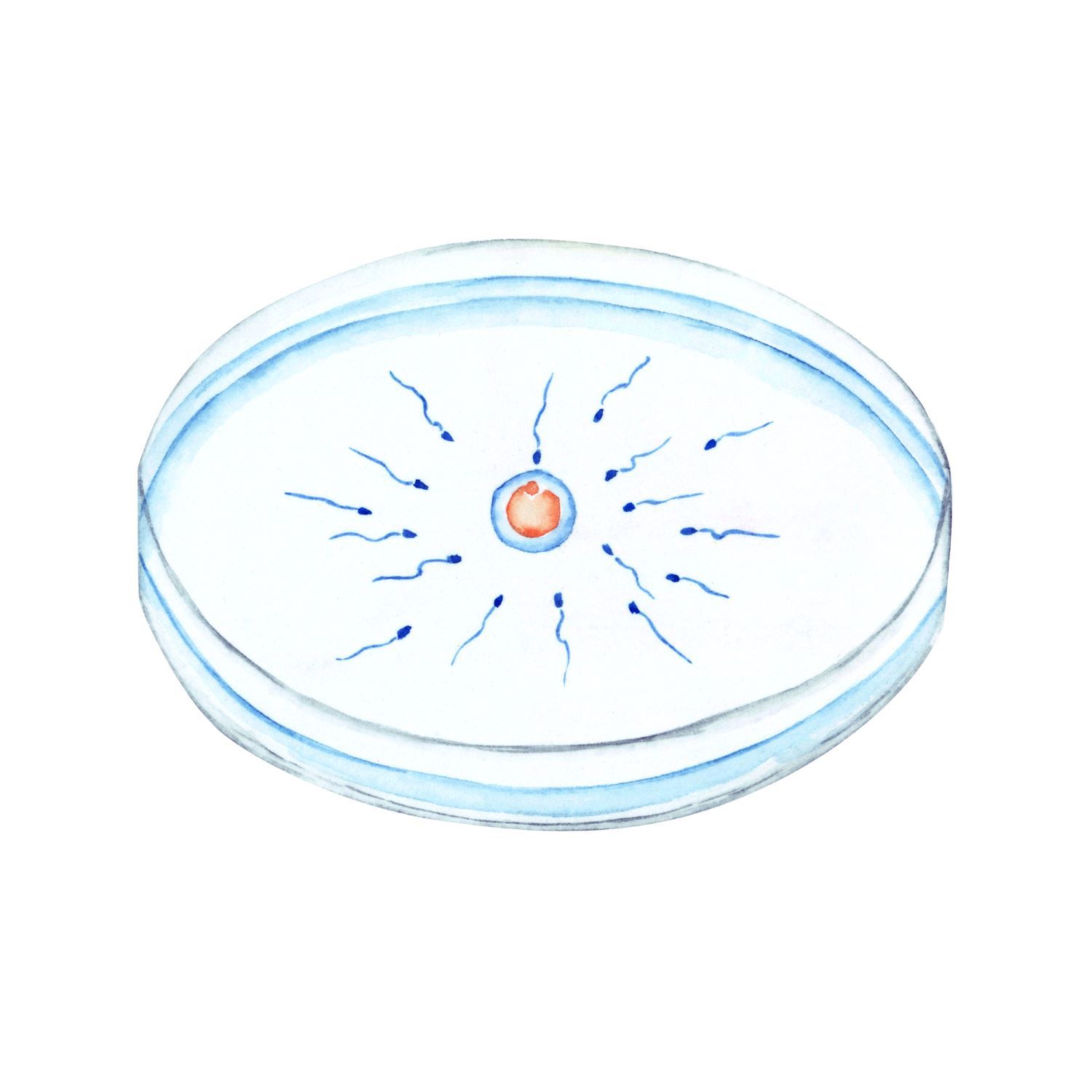
着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)とは?
着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)の基本的な仕組み
まず、着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)とは何かを先に解説していきます。
着床前胚染色体異数性検査(以下PGT-A)は、体外受精で得られた受精卵(胚)の染色体の数が正常かどうかを移植前に調べる検査のこと。
人間の染色体は通常23対(46本)ですが、受精卵の中には染色体の数が多すぎたり少なすぎたりするものがあります。このような受精卵は、移植しても着床しにくかったり、着床しても流産してしまう可能性が高くなります。
PGT-Aは、「染色体の数が正常な胚を選んで子宮に戻すことで、妊娠の可能性を高める」ことを目的に行われます。
検査の流れ
1. 体外受精で受精卵を作成
通常の体外受精と同じ方法で採卵した卵子と精子を受精させます。
2. 受精卵を5~6日間培
胚盤胞と呼ばれる段階まで成長させます。
3. 細胞を少量採取
将来胎盤になる部分から数個の細胞を採取します(赤ちゃんになる部分は傷つけません)。
4. 染色体の検査
採取した細胞の染色体数を専門機関で調べます。
5.結果に基づいて移植
検査結果に基づき、染色体が正常と確認された胚を子宮に戻します。
今回の細則改定で何が変わったの?
これまで(改訂前)のPGT-A対象者
以前は、細則の対象欄に「反復する」不妊治療の不成功や流死産という記載があり、以下の2つの条件のいずれかに当てはまる方のみが対象でした。
1. 体外受精で2回以上移植しても妊娠しない方
2. 2回以上の流産を経験している方
つまり、PGT-Aを受けられる方の対象が、「すでに何度か辛い経験をした方」に限定されていたのです。
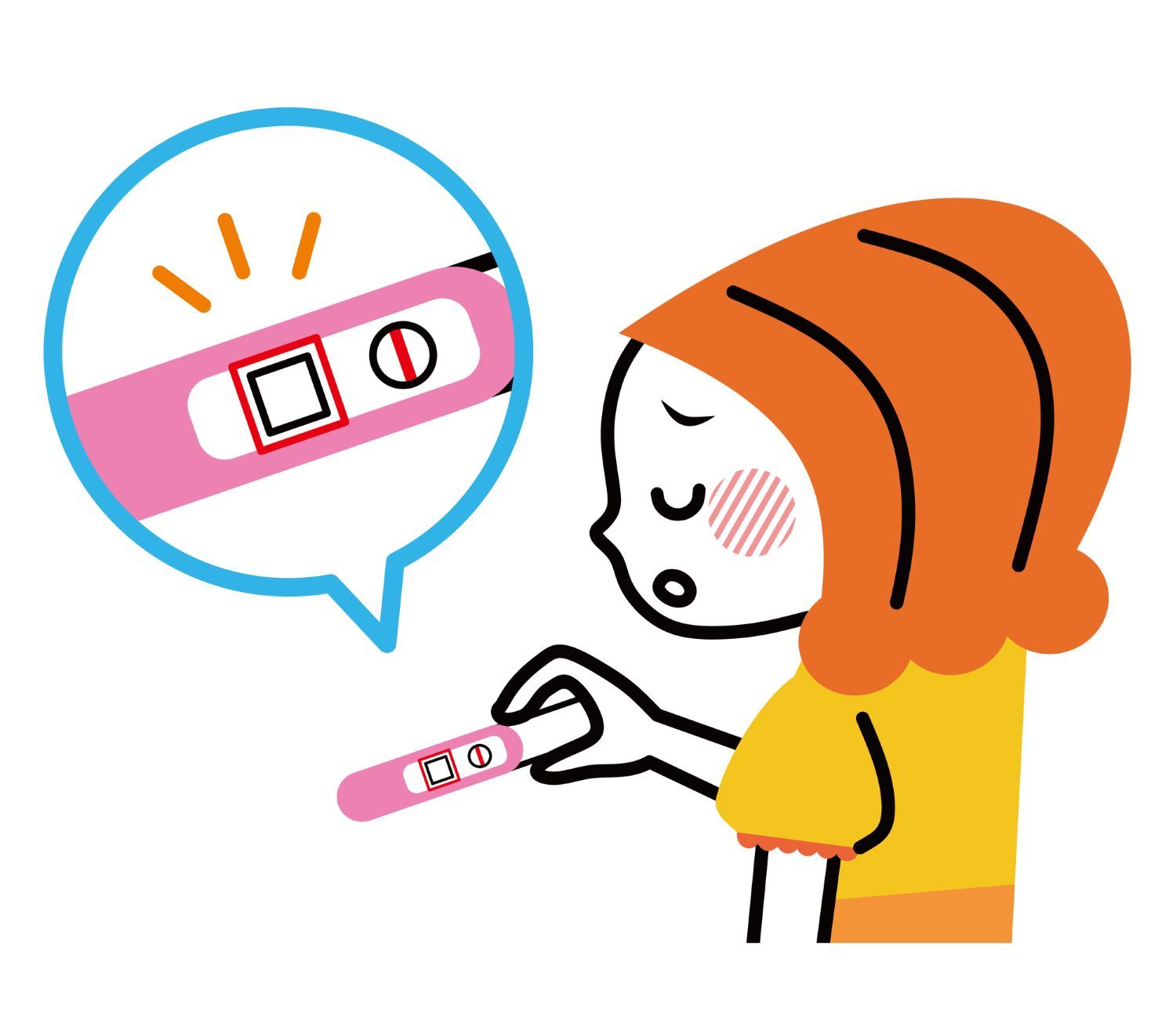
今回の改定で新しく追加された対象者は?
上記の2つに加えて、今回新たに追加されたのが、
3. 女性の年齢が35歳以上の不妊症の方
という記述です。これにより、35歳以上の女性は、過去の移植不成功や流産の経験がなくても、最初からPGT-Aを選択できるようになりました。
なぜ35歳以上が対象に加わったのか
年齢と染色体異常の関係
改訂に至る経緯については、今回の発表に記載があるのですが、女性の年齢が上がると、卵子の染色体異常が起こりやすくなることが医学的に分かっています。特に35歳を過ぎると、その割合が徐々に増加していきます。
最近の海外の研究では、35歳以上の女性の場合、PGT-Aを行うことで
●妊娠率の向上が期待できる
●流産率の低下が期待できる
という結果が報告されています。
若い年齢層では注意が必要
一方で、35歳未満の比較的若い女性の場合、PGT-Aを行うことでかえって妊娠率が下がる可能性があることも分かってきました。現在の論文で得られているエビデンスを元に、メリットの大きい世代を対象として加えたと解説されています。
PGT-Aのメリット、デメリットは?
PGT-Aを受けることのメリット
1. 流産のリスクを減らせる可能性
染色体異常による流産を避けられる可能性があります。
2. 移植あたりの妊娠率向上
染色体数の正常な受精卵により妊娠率が高くなる可能性があります。
3. 精神的・身体的負担の軽減
流産を繰り返すことによる心理的・身体的な負担を減らせる可能性があります。
PGT-Aのデメリット・注意点
1. 検査には限界がある
どの検査にも言えることですが、100%を保証するものではありません。検査で「正常」になった胚でも必ず妊娠するというわけではありません。検査で「異常」とされた受精卵でも、実際には妊娠・出産に問題ない場合もあります(細かい解説は本記事では避けますが、モザイクと呼ばれる状態)。
2. 費用負担(保険診療の治療を受けている方は要注意)
PGT-Aは保険適用外(自費診療)の検査です。体外受精の費用に加えて、検査費用が必要になります。特に、保険診療で不妊治療を受けている方には、混合診療になってしまうため併用ができない(全て自費診療になる)可能性がありますので注意が必要です。
3. 移植できる受精卵が減る可能性
検査の結果、移植に適さないと判定される受精卵が出てきます。すべての受精卵が「異常」と判定された場合、移植ができなくなる可能性もあります。
4. 検査による受精卵へのダメージ
検査のための細胞採取により受精卵がダメージを受ける可能性があります。
検査を受ける前に最低限知っておくべきこと

遺伝カウンセリングは必ず受けましょう
これはPGT-Aに限らず、すべての出生前検査に言えることですが、検査前の遺伝カウンセリングはとても重要です。PGT-Aを受ける際には、必ず専門医の遺伝カウンセリングを受けることになっています。専門の医師から、
●検査の意味と限界
●結果の解釈方法
●今後の治療方針
などについて詳しい説明を受け、十分に理解した上で検査を受けるかどうかを決めることが大切だからです。
性別は原則として教えてもらえません
PGT-Aでは技術的に性別も分かりますが、日本では原則として性別の情報は開示されません。これは、男女の産み分けに使われることを防ぐためです。
施設選びのポイントは?
PGT-Aは、日本産科婦人科学会から認定を受けた施設でのみ実施でき、産科婦人科学会のこちらの検索ページで検索できます。
認定施設には、
●生殖医療専門医が常勤している
●臨床遺伝専門医と連携している
●適切な検査機関と提携している
などの条件があります。
必ず医師と相談しよう
PGT-Aを受けるかどうかは、年齢、これまでの治療経過、受精卵の数、経済的な状況など、様々な要因を考慮して決める必要があります。担当医とよく相談して、パートナーとも十分に話し合ったうえで、ご自身で決めることが大切です。
まとめ|選択肢が広がった今、大切なことは?
今回の改定により、35歳以上の女性は最初からPGT-Aという選択肢を持てるようになりました。これは、不妊治療のより早い段階で流産のリスクを減らし、効率的な治療を受けられる可能性があることを意味します。
crumiiは、この改定は「産みたい」と思っている方の助けになるものだと考えます。
ただし、PGT-Aは万能ではありません。検査には限界があり、費用もかかります。また、すべての方に適しているわけでもありません。
大切なのは、正確な情報を得て、自分たちにとって最善の選択をすること。不明な点があれば、担当医に相談し、納得した上で治療方針を決めていくことをお勧めします。
以上、crumii医療記事解説でした!
にも解説して欲しいことがあれば、リクエストをお待ちしております。すべてのリクエストにお応えできるわけではありませんが、取り扱っていきたいと思います。
【参考資料】
「不妊症および不育症を対象とした着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)に関する細則」 の改定について
日本産科婦人科学会 不妊症および不育症を対象とした着床前遺伝学的検査(PGT-A・SR)















